<最終更新日>
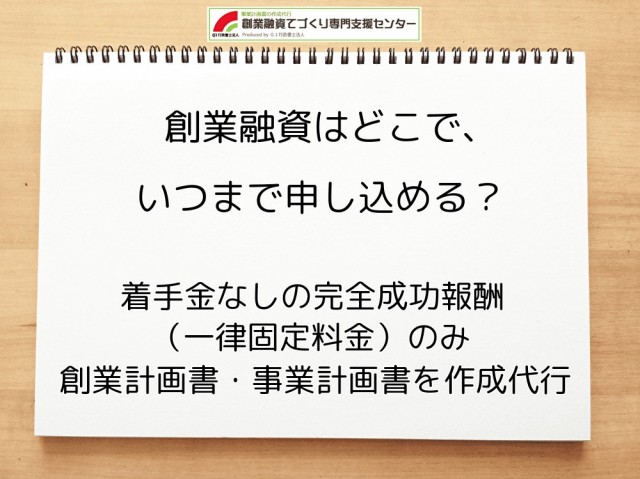
創業にあたって融資を受けたいと考えている方、特に「創業融資はどこで、いつまで申し込むことができるの?」という疑問をお持ちの方に向けて、創業融資を受けられる機関や申し込み時期などの基本情報から、日本政策金融公庫のサポート制度、審査に通過するためのポイントまで詳しくご紹介します。
創業融資とは、新しく事業を始める方や事業開始後間もない方が、必要な資金を調達するための融資制度です。
事業開始時には店舗・事務所の賃貸費用、設備・備品の購入費用、在庫仕入れ資金、人件費、広告宣伝費など様々な資金が必要になります。
多くの場合、自己資金だけではこれらの費用を賄いきれないため、金融機関や公的機関から資金を借り入れることが一般的な選択肢となっています。
創業融資は大きく分けて以下の3種類があります。
日本政策金融公庫(旧国民生活金融公庫)が代表的で、創業者向けの融資制度が充実しています。
民間金融機関と比較して審査基準が緩やかで、無担保・無保証人での申し込みが可能です。
都道府県や市区町村などの自治体が、地元の中小企業支援のために提供しているのが制度融資であり、この制度融資の一部として創業融資が実施されています。
自治体、信用保証協会、金融機関の三社が連携して資金を供給し、地域経済の活性化を目的としているため、地域によって条件や支援内容が異なります。
利子補給制度や信用保証料の補助など、さまざまな優遇措置が設けられていることが特徴です。
都市銀行、地方銀行、信用金庫、信用組合などが提供する融資については、一般的に政府系金融機関よりも審査基準は厳しい傾向です。
しかし、信用保証協会の保証を受けることで創業時でも融資を受けやすくなります。
また、最近では日本政策金融公庫との協調融資を行うケースも増えています。
創業融資の申し込み時期は、利用する制度によって大きく異なります。
それぞれの主要な融資制度について詳しく解説します。
日本政策金融公庫(公庫)は、政府系金融機関として多くの創業者に利用されている金融機関です。
特に創業期の事業者に対しては、手厚い支援が用意されています。
2024年3月に従来の「新創業融資制度」が廃止され、「新規開業・スタートアップ支援資金」制度に一本化されたことで、支援内容が拡充されました。
これにより、創業・開業する方への支援がさらに厚くなり、融資を受けやすくなっています。
新規開業・スタートアップ支援資金が利用できるのは、新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方です。
さらに、創業期(事業開始前または事業開始後税務申告を2期終えていない方)については、以下のような優遇措置があります。
■無担保・無保証人融資(審査による)
■基準金利からの利率引き下げ
■長期返済プランの設定
日本政策金融公庫の場合、創業前でも融資申請が可能です。
税務申告を2期終えていない創業期に申し込むことで受けられる優遇措置があるため、早めの申し込みを検討してください。
詳しくは、後述の日本政策金融金庫の創業融資をご覧ください。
都道府県や市区町村が提供する制度融資は、地域によって名称や条件が大きく異なります。
「開業地の都道府県(または市区町村) 創業」などで検索をしてみると、様々な名称でそれぞれの制度が用意されているので一度確認してみてください。
自治体の制度融資の特徴として、以下のような優遇制度が設けられていることもあります。
■信用保証料の一部または全額補助
■利子補給制度(利息の一部を自治体が負担)
■創業セミナーや経営相談との連携
いつまで申し込むことができるのかは各自治体によって設定が異なります。
一般的には、事業開始前から事業開始後3~5年以内などの期間設定になっていることが多いですが、自治体によっては申請期間が限定されていたり、予算に上限があったりする場合もあります。
そのため、開業予定地の地方自治体のウェブサイトや窓口で、最新の情報を確認することをお勧めします。
制度の内容は年度ごとに変更されることもあるため、直接問い合わせるのが確実です。
信用保証協会は、中小企業者が民間金融機関から融資を受ける際に、公的な保証人となる機関です。
信用保証協会の「保証付融資」を利用することで、創業時でも比較的審査の厳しい民間金融機関から融資を受けやすくなります。
また、創業者向けの特別な保証制度も用意されており、これらの制度では一般的な保証制度よりも条件が緩和され、創業者が融資を受けやすくなっています。
いつまで申し込むことができるのかの時期については、事業開始前または事業開始から5年未満となっていますが、自治体の制度融資と連携している場合も多いため、地域の信用保証協会や取引予定の金融機関に確認することをお勧めします。
創業融資のプロセスは、「申し込み→審査→融資実行→返済」という流れになります。それぞれの期間について詳しく見ていきましょう。
創業融資の審査期間は、申し込む機関や融資の種類によって異なりますが、一般的に約2週間~2ヶ月ほど掛かります。
ただし、書類の不備や追加資料の提出依頼があった場合は、さらに時間がかかることがあります。
また、繁忙期(年度末など)には審査に時間がかかる傾向があるため、余裕をもって申し込みましょう。
審査が通った後、実際に資金が振り込まれるまでの期間についても申し込み期間によってさまざまですが、一般的には審査承認後約1週間~1ヶ月が目安です。
ただし、担保設定や保証人の手続きが必要な場合は、さらに時間がかかることがあります。
融資が実行されるタイミングについては、申し込み時に金融機関に確認しておくと安心です。
返済期間も融資制度によって大きく異なります。例えば、日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」については以下のように定められています。
■設備資金:最長20年(うち据置期間最長5年)
■運転資金:最長10年(うち据置期間最長5年)
日本政策金融公庫の創業融資は、相対的に返済期間が長く設定できる要件になっているため、月々の返済負担を抑えることができます。
また、据置期間(元金の返済が猶予される期間)が設けられていることも大きな特徴です。
創業初期は収益が安定しないことが多いため、据置期間を設けることで、事業が軌道に乗るまでの資金繰りを緩和することができます。
創業融資の条件は事業計画や審査結果によって個別に設定されるため、具体的な条件については申し込み時に確認しましょう。
日本政策金融公庫は、創業者にとって最も利用しやすい融資制度を提供している機関の1つです。
ここでは、2025年3月に変更された創業融資「新規開業・スタートアップ支援資金」について詳しく解説します。
日本政策金融公庫では、従来の「新創業融資制度」を2024年3月に「新規開業資金」へ一本化し、2025年3月からは「新規開業・スタートアップ支援資金」という制度名で開業前および開業後の事業者向けに資金提供を行っています。
主な変更点は以下のとおりです。
【旧】新創業融資制度
■無担保・無保証人での融資が可能
■融資限度額:3,000万円(うち運転資金1,500万円)
■自己資金要件:創業資金総額の10分の1以上
【新】新規開業・スタートアップ支援資金(旧新規開業資金)
■無担保・無保証人での融資が引き続き可能(審査による)
■融資限度額:7,200万円(うち運転資金4,800万円)に拡大
■自己資金要件:撤廃
■女性、若者(35歳未満)、シニア(55歳以上)、創業に再チャレンジする方など幅広い層の創業者に対応
■事業化支援・経営支援の強化
日本政策金融公庫の創業融資「新規開業・スタートアップ支援資金」は、新たに事業を始める又は事業開始後おおむね7年以内の方であれば申し込みが可能です。
ただし、より有利な条件で融資を受けるためには「創業期」に申し込むことが大切です。
日本政策金融金庫による創業期の定義は、事業開始前又は事業開始後税務申告を2期終えていない状態です。
創業期に該当する場合、以下のような優遇措置を受けることができます。
■無担保・無保証人融資
創業期には無担保・無保証人で融資を受けられる可能性が高くなります。
■利率の優遇
創業期には、基準金利から一定の引き下げが行われることがあります。
■長期返済プラン
創業期の事業者向けに、返済期間の長期化が図られています。
さらに、創業融資の申し込み時期を開業前にするか開業後にするのかも大切なポイントです。
下記に主なメリットとデメリットをまとめました。
■開業前の申し込み
メリット:準備段階から資金を確保できるため、余裕をもって創業準備を進められる
デメリット:実績がないため審査では事業計画の説得力が重要になる
■開業後の申し込み
メリット:実績を示せるので事業の実現性をアピールしやすい
デメリット:開業資金を自己資金で賄う必要がある。創業期の優遇を受けられる期間が短くなる
理想をいえば、ある程度の自己資金を用意した上で、開業前または開業直後に申し込むことで創業期の優遇措置を最大限に活用することができます。
Q:新規開業・スタートアップ支援資金(新規開業資金)を断られた場合、再度申し込むことは可能?
A:日本政策金融公庫の創業融資審査に落ちた場合でも、再度申し込みをすることは可能です。
ただし、前回の審査で指摘された問題点を改善していないと、再度の審査でも同じ結果になる可能性が高いです。
審査で不利になる主な要因の例は以下のような内容です。
■改善が可能な要因の例
・創業計画書の不備
・事業の実現性に疑問がある
・収支計画が非現実的
・市場分析が不十分
・事業経験やスキルの不足
これらの場合は、問題点を改善した上で再申し込みすることで、審査通過の可能性が高まります。
■改善が難しい要因
・犯罪履歴がある
・反社会的勢力との関係がある
・多額の借入や債務整理の履歴がある
これらの場合は、融資を受けることが極めて困難です。
また、信用情報に問題がある場合は、個人信用情報機関からの情報が消えるまで数年は待つ必要があります。
専門家からアドバイスを受けることによって創業計画書をブラッシュアップし、事業の信頼性と実現性を第三者に明確にアピールすることができますので、まずはお気軽にご相談ください。

Q:法人成りによって事業開始日はリセットされる?
A:法人成りは、個人事業主が「株式会社」や「合同会社」などの法人を設立して事業を行うことを指しますが、このような場合は事業開始日はリセットされません。
日本政策金融公庫の創業融資では「新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内」という要件がありますが、個人事業主は開業届を提出した時点から事業開始とみなされ、その後に法人化しても、事業そのものの開始時期は変わらないという考え方になります。
ただし、全く別の事業を始める場合や、法人の事業内容が個人事業と大きく異なる場合は、新たな創業とみなされる可能性もありますので、専門家や日本政策金融公庫の窓口で相談することをお勧めします。
新規開業・スタートアップ支援資金の申し込みタイミングについて詳しく解説してきましたが、申し込みをしても審査に通過しなければ計画通りのタイミングで融資を受けることができません。
そこで、最後に審査に通過するために重要なポイントをいくつかご紹介します。
一般的に金融機関が融資審査で重視するのは、返済能力と事業の実現性です。
それでは詳しく見ていきましょう!
新規開業・スタートアップ支援資金では自己資金要件は撤廃されましたが、審査においては依然として自己資金の割合は重要な評価ポイントになると考えられます。
■ポイント
・希望融資額が多いほど、事前に自己資金を多く確保する
・不自然な大口の入金(親族からの借入など)は避ける
目安としては、創業資金総額の目安として1/3程度を自己資金で準備できると望ましいですが、事業内容や規模によっても異なります。
自己資金が少ない場合は、その分事業計画の精度を高めて実現性をアピールすることが重要です。
自己資金の詳細はこちらの記事でご紹介していますのでご覧ください。
<自己資金なしで創業融資を受けることはできるのか解説!>
創業計画書は、創業融資の審査において最も重要な資料です。
特に以下の点に注意して作成しましょう。
■収益計画と売上予測の妥当性
・売上予測は根拠を明確にし、現実的な数字を設定する
・資金繰り表で月ごとの収支を詳細に示す
■市場分析と差別化戦略
・ターゲット顧客を明確に定義する
・マーケティング戦略を具体的に説明する
・将来的な事業展開や成長戦略を具体的に示す
創業融資の審査では、経営者自身の能力や経験も重要な評価ポイントとなります。
■業界経験がある場合
・業界での経験年数や役職などを具体的に記載する
・取引先や顧客との関係性を示す
■業界経験がない場合
・これまでの他業界での経験が現在の事業にどう活かせるかを説明する
・経営者としての熱意や学習意欲を伝える
ただし、創業する事業の業界経験がない場合は、審査に通る可能性が非常に低くなってしまう傾向にあります。
また、創業融資の審査通過率を高めるために、専門家のサポートを活用することが非常に効果的です。
専門家は創業計画書の作成代行・支援から融資申請のアドバイスまで様々な面でサポートを行っています。
金融機関や補助金の審査側の判断基準を熟知し、第三者の視点で説明不足や説得力の弱さを補うことで書類の完成度が一段アップすることが可能になりますので、まずはお気軽にご相談ください。
本記事では、創業融資はどこで、いつまで申し込めるのかについて解説しました。
創業融資は利用する制度によって異なりますが、それぞれ以下のポイントを押さえることが重要です。
①日本政策金融公庫の場合
創業期(事業開始前または事業開始後税務申告を2期終えていない状態)に申し込むことで、無担保・無保証の融資や利率の優遇などの恩恵を受けられます。
②自治体の場合
各自治体によって条件が異なるため、開業予定地の自治体に直接問い合わせて最新情報を確認することが重要です。
③信用保証協会(民間金融機関)の場合
事業開始前または事業開始から5年未満であれば基本的に利用可能ですが、自治体の制度融資と連携している場合も多いため、地域の信用保証協会に確認することをお勧めします。
審査通過のポイントとしては、自己資金の充実、創業計画書の精度向上、経営者としての経験・スキルのアピールが重要です。
専門家による創業計画書のブラッシュアップは審査通過の可能性を高める1つの手段になりますので、ぜひご検討ください。
創業融資は、事業の立ち上げ期における重要な資金調達手段です。計画的に準備を進め、十分な情報収集と相談を行った上で申し込むことで、事業の成功に向けた第一歩を踏み出しましょう。
創業融資てづくり専門支援センターでは、これまで4,500件以上の創業融資サポート・創業計画書・事業計画書の作成サポートを提供しており、その経験とノウハウを活かして、着手金なしの完全成功報酬(一律固定)にて対応させていただいております。
創業融資に関心をお持ちの方や、資金調達や開業資金集めなどの方法でお悩みの方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。

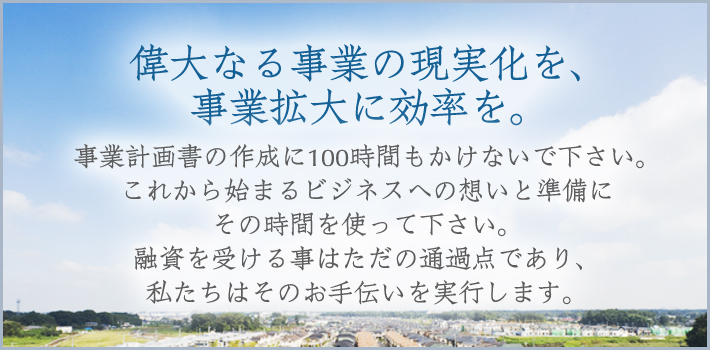
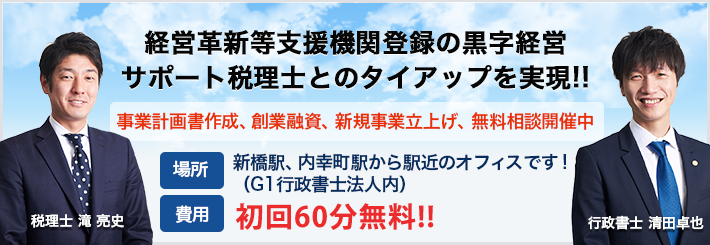
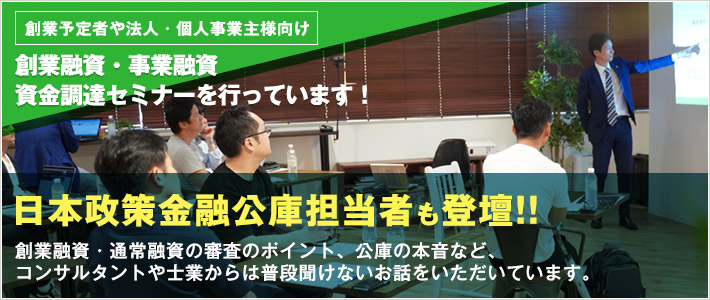



東京本社
〒100-0005
東京都千代田区丸の内1丁目1番1号
パレスビル5階
大阪支社
〒541-0046
大阪府大阪市中央区平野町3-2-8
淀屋橋MIビル3階
TEL / 0120-3981-52
FAX / 03-4333-7567
営業時間 月~土 9:00~20:00
メール問い合わせ 24時間対応

創業融資てづくり専門支援センター長の行政書士清田卓也でございます。
当センターは親切、丁寧、誠実さをモットーに運営しております。
事業計画書の作り方から創業融資まで、起業家・経営者様のほんのちょっとした疑問にもご対応させていただいております。
お気軽にご連絡下さい。