<最終更新日>
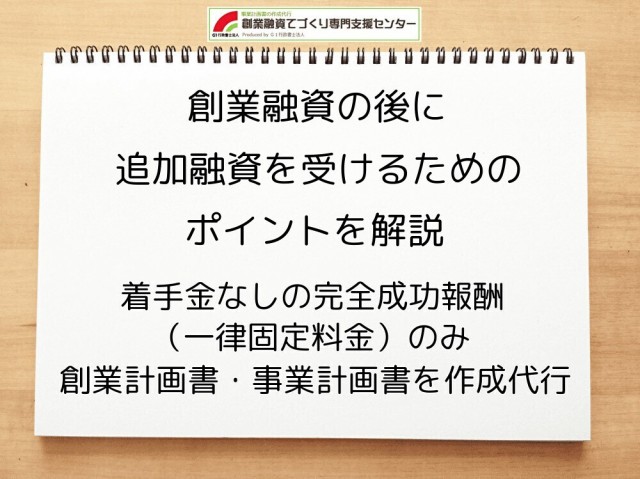
日本政策金融公庫の創業融資を利用したことがある方で、追加の融資を受けたいとお考えの事業者様はいらっしゃいませんか。
創業融資を受けたあとに、追加融資を申し込むことは可能ですが、初回融資とは異なる点や、審査に際しての注意事項などがいくつか存在します。
そこで今回は、日本政策金融公庫から追加融資を受けるためのポイントを解説していきます。
追加融資とは、一度創業融資を受けた金融機関に対して文字どおり追加の融資を申し込むことを言います。
既存の融資の返済中に新たな融資を申請することになり、借入総額が増加することになるため、追加融資の可否は支払能力に左右されます。
初回の創業融資では代表者の経歴や実績、取扱商品・サービスの独自性や自己資金の有無など、創業する事業にどの程度成長見込みがあるかといった点が審査において重要視されます。
これに対して、追加融資では初回と異なり「これまでの売上」「利益」「収益の向上性」など、事業の現状も踏まえて審査されます。
そのため、既存事業の実績が不十分な場合は追加融資の審査が通りにくくなる場合があります。
追加融資を受けるメリットはいくつかありますが、まず一つは「スムーズに資金調達を行える可能性が高い」という点です。
基本事項の確認は初回の創業融資時に完了しているため、追加融資の場合は審査が比較的円滑に進むことが多いです。
そのため、なるべく早く資金を調達したい方にとっては有用な資金調達手段であると言えます。
また、資金が増えることで想定しているスケジュールどおりにビジネス展開を行えるのはもちろんのこと、更なる事業拡大に向けた設備や販売戦略などにも投資ができるようになるため、より一層の収益向上を見込むことが可能になります。
追加融資を受けるデメリットは、単純に「借入総額が増える」という点です。
返済期間も追加で融資を受けた分長くなり、返済の負担が重くなるというリスクを抱えることになります。
また、借入総額が増える分、他の金融機関からは融資を受けにくくなる恐れもあります。
追加融資を申し込む際は、場当たり的に利用を決めるのではなく、事前に返済計画をしっかりと立てておくことが重要です。
追加融資を受ける際の流れは、以下のとおりです。
まずは前回創業融資を受けた日本政策金融公庫の窓口へ相談に行きます。
この時に以前の担当者が分かる場合は、その担当者宛てに直接確認すると、より円滑に進められるでしょう。
窓口での相談時は、追加融資を希望する旨と併せて、追加融資がどのような理由で必要であるかを具体的に説明できるようにしておくのが望ましいです。
必要書類を準備・提出します。
不備があると審査に通らない可能性がありますので、担当者の指示に従い正確に書類を用意する必要があります。
また、追加資料の提出を求められる場合があることも念頭に置いておきましょう。
なお、必要書類の詳細については後ほど解説します。
必要書類を提出した後は、面談が行われます。
追加融資の際は、初回の融資と異なり必ずしも対面で面談が行われるとは限らず電話で実施されるケースもあります。
事前に担当者へ確認し、しっかりと準備しておくようにしましょう。
面談では現在の経営状態についてや返済の意思などが確認されるため、これらにもきちんと答えられるようにすることが大切です。
追加融資の結果は、書類の確認などに時間を要する場合は3週間以上かかることもありますが、通常は1~2週間で可否の結果がわかります。
融資決定後は日本政策金融公庫から契約書類が郵便で届きますので、内容を記載(署名・捺印)して返送・提出します。
諸手続きが滞りなく行われた場合は、1か月以内に追加融資を受けることができます。
追加融資を受ける際に必要となることが多い書類は、下記のとおりです。
| 書類 | 注釈 |
| 本人確認書類 | 運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなどを用意しましょう。 |
| 決算書・確定申告書 | 法人の場合は決算書一式、個人事業主の場合は確定申告書を準備します。直近2~3年分を用意するようにしましょう。 |
| 見積書 | 設備資金を申請する場合は予め見積書を取得しておきましょう。 |
| 納税していることが証明できる書類 | 所得税や法人税の「納税証明書」、住民税や固定資産税の「課税証明書」などが必要になります。 |
| 売上を証明できる書類 | 明細書、試算表、資金繰り表など、毎月の売上実績や今後の見込みなどがわかる書類を用意します。 |
| 通帳 | 融資の返済実績や収益状況など資金の動きが確認できる通帳を準備しておきましょう。 |
| 返済予定表 | 住宅ローンや教育ローンなど、他の金融機関から借り入れを行っている場合に提出が必要です。 |
| 事業計画書 | 初回の創業融資で提出した創業計画書と乖離がある場合は、それらも理解してもらえるよう、乖離した要因や変更理由、対策なども加味した内容であることが望ましいです。 |
前述のとおり、追加融資の審査では売上や収益などから返済能力があるかといった点が確認されるため、これらの要素を示せる書類の提出が重要になってきます。
また、提出書類は事業状況などによっても変わってくるため、上記以外の書類を求められる場合もあります。
実際にどのような書類が必要になるかは、担当者の指示に従うようにしましょう。
追加融資の際の審査のポイントはいくつかありますが、主要なものは以下のとおりです。
追加融資の審査においてまず重要視されるのが、既に受けている創業融資の返済をきちんと行っているか、という点です。
当然ながら、既存分の返済が遅延したり滞っていると追加の融資を受けることが難しくなりますが、さらに借入総額のうち3分の1以上を返済している状況が望ましいです。
追加融資の必要な理由がはっきりしているかも、審査においては重要なポイントです。
初回の創業融資金が適切に使われているかといった点に加え、
・何故前回融資した資金では足りないのか
・追加の融資を受けるにあたって、何にいくら使いたいのか
などの内容が確認されることになりますので、しっかりと答えらえるようにする必要があります。
この際、資金繰り表や事業計画書などの資料を基に説明することで、担当者へ資金使途を伝えやすくなります。
追加融資を申し込む際は、少なくとも1期が経過し決算書がある状態にしておくことが望ましいです。
これは、決算書がある方が日本政策金融公庫の担当者も事業の実態を把握しやすくなるためです。
試算表でも申し込みは可能ですが、不確定要素が多く暫定的な書類であると見なされる傾向にあり、決算書に比べると信頼度が下がることから、追加融資の結果にも影響する可能性があります
「資金が早急に必要」というわけでなければ、1期目が終わり、決算書が用意できてから追加融資を申請するのが良いでしょう。
安定した事業運営をできているかという点も追加融資では審査されます。
こちらに関しては財務情報などから判断されることが多く、売上や利益が着実に伸びていればその分追加融資の審査が承認される確率も高くなります。
ここまでで追加融資を受けるための流れやポイントをお伝えしましたが、残念ながら追加融資を受けられないケースも存在します。
ここからは、どのようなケースだと追加融資に落ちることが多いのかを解説します。
赤字が2期以上続いている場合は、追加融資の審査に通らない可能性が高くなります。
前述のとおり、追加融資ではこれまでの実績や財務状況などを通して返済能力の有無が判断され、赤字決算が慢性化していると支払能力が欠如しているとみなされるためです。
収益がマイナスであったことについて相当の理由があった旨や、適切な打開策を説明できれば赤字でも追加融資が認められることもありますが、継続的な赤字や損失額の増加が見られ、かつその背景や対策を有効に説明できない場合は追加融資を得るのは困難と言えます。
他の金融機関などからの借入額が増えている場合は、追加融資の審査が通らない可能性が高まります。
借入総額が多いとその分月々の返済額が多くなるため、返済能力を見極めるうえで重要な項目となり、日本政策金融公庫以外の金融機関からの借入も含めて判断されます。
既存融資の返済が滞っていると、追加融資もきちんと返済されないと判断されて追加融資を受けられない可能性が高くなります。
また、日本政策金融公庫は政府系金融機関であることから、納税状況なども厳格に審査されるため、税金の未払いなどがある場合も追加融資審査の障壁となり得ます。
何かしらの事情で追加融資を受けられない場合は、他のルートでの資金調達を検討するのも手段の一つです。
当センターがおすすめさせていただくことが多い方法としては、「補助金の活用」があります。
補助金を利用するメリットの一つに、融資とは違い返済の義務が無いという点があります。
補助金も目的や金額に応じて多種多様なものが設けられていますが、今回は中小企業や小規模事業者の方から利用されることが多い補助金の例として以下をご紹介します。
■小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金は、販路開拓や業務効率化に取り組む小規模事業者の支援を目的とした補助金制度です。
補助金額に関しては通常枠では上限50万円(補助率2/3)となっています。
すなわち、75万円の経費で申請した場合、その内の50万円が補助され、自己負担は実質25万円で済むということになります。
近年は法改正や最低賃金の引き上げ、インボイス制度への対応など、小規模事業者にとってコストを割かざるを得ない外的要因が増え、販路開拓に十分な予算を充当できない状況が続いています。
こうした中でもこの補助金を活用することで、限られた資金で販路拡大やIT化に向けての積極的な取り組みを行うことが可能になります。
※持続化補助金の詳細はこちらの記事もご覧ください。
<小規模事業者持続化補助金一般型>
■IT導入補助金
IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者が業務効率化やデジタル化を進めるためのITツール(ソフトウェアやクラウドサービスなど)を導入する際の費用の一部を支援する補助金です。
この補助金の狙いは、ITツールの導入を通して中小企業・小規模事業者が労働生産性の向上を図ることにあります。
補助の対象となるのは、事務局の審査を通過して予め登録されたITツールに限られます。
また、実際の申請にあたっては、IT導入支援事業者(ITツールの販売・提供を行うベンダー・サービス事業者)と連携して行う仕組みとなっており、このIT導入支援事業者も、事前に事務局からの審査と登録を受けている必要があります。
なお、IT導入補助金は事業開始初年度(初年度の決算・納税がまだ)には申請できませんので、創業間もない方や法人は2期目以降で活用を検討しましょう。
各種補助金申請に関しても当センターでサポートを提供しておりますので、ご興味のある方はぜひお気軽にお問い合わせください。
※補助金情報サイトも別途運営しておりますので、詳細はこちらの記事もご覧ください。
<IT導入補助金の解説>
<持続化補助金の解説>
今回は、一度創業融資を受けたことがある方が追加融資を受けるためのポイントをご紹介しました。
追加融資の申請は、初回融資の際と比べて異なる点や、細かな注意事項などもありますので、申し込みの際は事前に確認しておくようにしましょう。
当サイトを運営する創業融資てづくり専門支援センターでは、これまでトータル4,500件以上の創業融資サポート・創業計画書・事業計画書の作成支援実績があります。
豊富なナレッジや経験をもとに、着手金なしの完全成功報酬(一律固定料金)にて綿密なサポートを提供することが可能です。
創業融資を検討されている方や、金銭面や開業資金などについてお悩みの方は、ぜひ一度、お気軽にお問い合わせください。

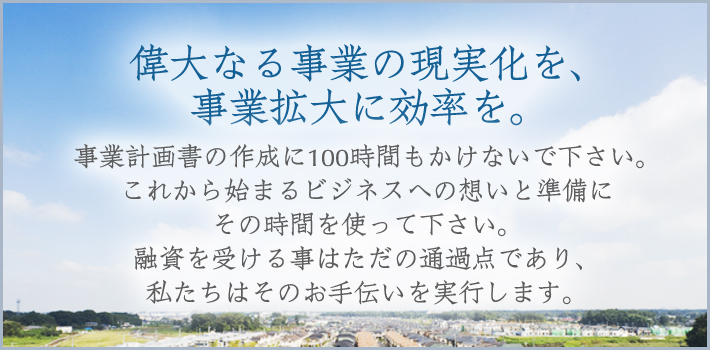
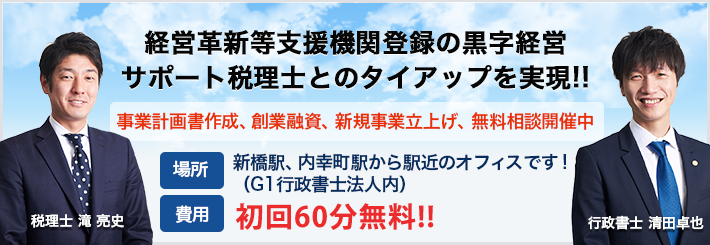
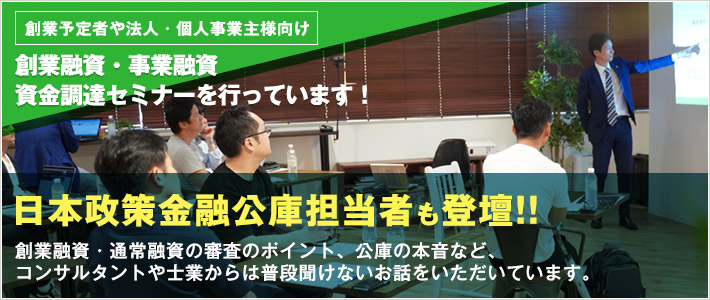



東京本社
〒100-0005
東京都千代田区丸の内1丁目1番1号
パレスビル5階
大阪支社
〒541-0046
大阪府大阪市中央区平野町3-2-8
淀屋橋MIビル3階
TEL / 0120-3981-52
FAX / 03-4333-7567
営業時間 月~土 9:00~20:00
メール問い合わせ 24時間対応

創業融資てづくり専門支援センター長の行政書士清田卓也でございます。
当センターは親切、丁寧、誠実さをモットーに運営しております。
事業計画書の作り方から創業融資まで、起業家・経営者様のほんのちょっとした疑問にもご対応させていただいております。
お気軽にご連絡下さい。