<最終更新日>
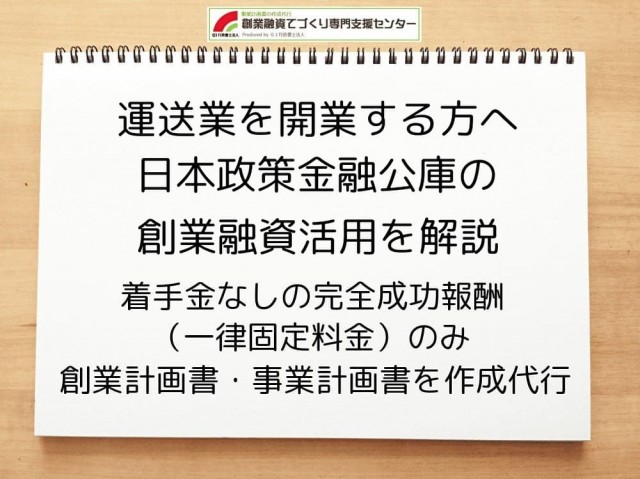 運送業の創業・開業を目指す方にとって大きな課題の一つとなるのが、「資金をどう工面するか」という点です。
運送業の創業・開業を目指す方にとって大きな課題の一つとなるのが、「資金をどう工面するか」という点です。
事務所など物件取得に必要な費用や営業に使用する備品の代金、また創業してから数か月間の運転資金など、創業・開業段階はある程度の資金が必要となるものの、その全額を自己資金でカバーするのは難しいという方もいるかと思います。
そのようなときに活用をおすすめしているのが、日本政策金融公庫の創業融資制度です。
創業融資は、新規で事業を開始したい方が主な利用対象で、無担保無保証かつ低金利で長期間返済が行えるという点が魅力の融資制度です。
この記事では、運送業の創業・開業を検討している方に向けて、日本政策金融公庫の創業融資の詳細を解説していきます。
日本政策金融公庫は、政府系金融機関として多様な資金ニーズに対して融資を実施しています。
特に、創業・開業段階の方や創業したばかりの方に向けては、無担保・無保証で利用可能な創業融資制度を提供していることから、日本政策金融公庫の創業融資は創業に際しての有力な資金確保の方法として多くの創業者から活用されています。
日本政策金融公庫の創業融資にもいくつか種類がありますが、運送業の開業時に利用される制度は「新規開業・スタートアップ支援資金(新規開業資金)」です。
この創業融資制度は、無担保・無保証で借り入れられるという特徴があり、これから事業を開始する方または事業開始後おおむね7年以内の方が利用可能です。
運送業の創業にあたり創業融資に申し込むには、「創業計画書」の提出が必要となります。
創業計画書は、作成する前に情報の整理を入念に行い、論理性と実現性を兼ね備えた内容であることが重要ですので、以下で解説する点を押さえて創業計画書を作成するようにしましょう。
創業の動機には、なぜ運送業を創業したいと考えたのか、その目的や背景を記していきますが、この際、自分がこれまで積み上げてきた経験や強みなどもアピールすると説得力が増します。
また、創業に向けてどのような準備をしてきたのかという点や、見込顧客や既存顧客がいること、創業場所の地域の特性なども記載するとより効果的です。
更に、マネジメントや従業員の教育などに携わったことがある場合は、その旨も併記しておくことを推奨します。
高校や専門学校などの卒業年月日やこれまでの勤務先、そこでの勤続年数などの基本的な情報に加えて、これまでの担当業務や必要スキル、役職なども具体的に記入していきます。
創業者自身が車の運転も行う場合、事業の規模や内容によっては普通自動車免許以外の車種の免許も必要になる場合がありますので、その場合は「取得資格」の欄にそれらの取得状況も併記するようにしましょう。
「取扱商品・サービス」の欄には、運送の範囲や使用する車種、料金モデル、強み、ならびに経営戦略などを詳しく記載します。
ビジネスモデルをわかりやすく説明できるよう、収益の仕組みや対象となる顧客層も示すようにしましょう。
また、競合との差別化ポイントをしっかりと記載することも重要です。
例えば「取り扱いが難しい荷物や危険物の運送に長けている」「他社にはない独自のルートを確保できる」といった特徴がある場合は、それらをアピールするのも効果的です。
「取引先・取引関係等」には、例えばサービスを販売する見込みのある顧客や、燃料補給等を依頼する仕入れ先の業者などを記入します。
サービスを販売する見込みのある顧客は、見込み顧客との関係性や取引条件など取引が見込まれる理由を記載することで、収益の見通しに説得力を持たせることができます。
また、仕入れ先に関しては、その会社が知人の運営する企業であったり、過去の職場での取引先などである場合は、その関係性も記載することで信頼性の向上に繋がります。
「必要な資金と調達方法」の欄は、審査において特に入念に確認される部分です。
このため、創業に必要な資金(設備資金・運転資金)の額と、その調達方法はなるべく具体的に記入しましょう。
運送業で設備資金に該当するものとしては、例えばトラックの代金や物件取得費、パソコン、Webサイト製作費などが当てはまります。
単価が10万円以上のものに関しては必ず見積書を用意し、見積先の企業名と詳細な金額も記載しましょう。
次に、運送業で運転資金に該当するものは、燃料費や事務所などでの光熱費、人件費、通信費などがあります。
運転資金に関しても、ざっくりとした記載ではなく相場価格などに基づいた、正当な根拠のある金額を記すようにしましょう。
また、創業融資の審査では自己資金割合も非常に重要なポイントとなり、自己資金をどれだけ準備できているかを記入する欄(「調達の方法」の箇所)が創業計画書にも設けられています。
そのため、自己資金は申し込みをする前に可能な限り多めに用意しておくことをおすすめします。
「事業の見通し」は、将来の収支予測を示す欄となり、「創業初期」と「1年後(あるいは事業が安定する時期)」の2パターンの「売上高」「原価」「経費」「利益」などを月ごとの平均で記載していきます。
ここで押さえておくべきポイントは、それぞれの数値にきちんと根拠を持たせ、またその算出方法(計算式)も明確にすることです。
収益の見通しに実現性がなかったり、設定した経費が相場から極端にずれていたりすると、事業計画の信頼性が低くなり審査においてマイナスに作用することもありますので注意しましょう。
■自動車免許
創業者がドライバーも担当するとは限らないため、厳密に言うと運送業の創業に際して自動車免許が必須というわけではありませんが、創業者自身も運転ができる状況にしておくと創業後何かと安心です。
運送業で運転の際必要になる主要な免許としては以下が挙げられます。
事業の規模や内容に合わせて、必要な免許を取得しておくようにしましょう。
●普通自動車免許:軽貨物車や、小型車両を使った運送業務の際に必要になります。
●準中型免許:2トン~3トン未満のトラックを運転する場合に必要になります。
●中型免許:最大で4トンまでのトラックを運転する場合に必要になります。
●大型免許:4トン以上の大型トラック・トレーラーを運転する場合に必要になります。
■運行管理者
運送業の創業においては、営業所ごとに最低1人の運行管理者を置くよう定められています。
運行管理者は、車両の配車や勤怠を始めとしたドライバーの管理を行います。
また、運送業者が運送業務を行う前には、点呼によるドライバーの健康・疲労状態の確認をする必要がありますが、この点呼業務も運行管理者の仕事の一つです。
このように運行管理者は安全な運行を指示するための役割を担っており、資格を取得するためには運行管理試験に合格する必要があります。
ドライバーが運行管理者を兼任することも可能ですが、点呼業務は別の運行管理者か、運行管理補助者が行わなければなりません。
よって、営業所に運行管理者が1人しかいない場合や、運行管理補助者がいない場合は、運行管理者がドライバーを兼任することはできないということになりますので、注意しましょう。
■運行管理補助者
運行管理補助者を置くことで運行管理者の点呼業務を別の従業員でも代理できるようになるため、より柔軟な業務体制を築くことが可能になります。
運行管理補助者は、国土交通大臣が認定する「運行管理者基礎講習」を修了することで取得できます。
ただし、運行管理補助者はあくまで運行管理者のサポート役であり、運行管理者の代わりに全業務を行えるわけではありません。
例えば、点呼を行った結果の酒気帯びや体調不良など、安全に運送業務を行えない恐れのある事態が生じた場合でも、運行管理補助者が単独で判断してドライバーに指示を与えることは出来ず、運行管理者の判断や指示が必須となります。
また、運行管理補助者が行える点呼の回数は、月間の総点呼回数の3分の2未満までとなりますので、この点にも注意が必要です。
■一般貨物自動車運送事業許可
運送業の創業に際し特に重要なのが、「一般貨物自動車運送事業許可」です。
一般貨物自動車運送事業とは、他人からの依頼に応じて料金を受け取り自動車で荷物を運ぶ事業のことで、一般的な運送業者はほとんどこれに当てはまります。
※ただし、三輪以上の軽自動車や二輪の自動車で運送業務を行う場合は除外されます。
一般貨物自動車運送事業を始めるには、必要要件を満たしたうえで国土交通省から「一般貨物自動車運送事業許可」を得る必要があります。
審査においては実地調査なども実施されるため、申請の際にはきちんと準備をしておくことが重要になります。
■貨物軽自動車運送事業の届出
個人事業主が運送業を始める場合、貨物軽自動車運送事業として創業する場合が多くあります。
貨物軽自動車運送事業とは、三輪以上の軽自動車か、二輪車で他人からの依頼に対し有料で荷物を運ぶ事業のことで、一般的に「黒ナンバー」とも呼ばれています。
軽車両やバイクを使うため、少ない初期費用で事業を開始できるという特徴があり、一般貨物自動車運送事業と違って許可もいりませんが、役所に届出は出す必要がありますので注意しましょう。
日本政策金融公庫の創業融資に申し込むための条件には、次のようなものがあります。
■創業前または創業後おおむね7年以内であること
■創業計画書(事業計画書)を作成し、面談でもその内容を伝えられること
■クレジットカード、ローンなどの支払いが良好に行われていること
また、自己資金の保有状況や創業計画書にどのような情報が記載されているかといった点も、創業融資審査で重要視される項目になります。
融資額の条件に関して、「新規開業・スタートアップ支援資金」では設備資金で最大2,400万円まで、運転資金は最大4,800万円まで借り入れることが可能です。
また、返済期間の条件は次のように決められています。
■設備資金:最長20年(据置期間最長5年以内)
■運転資金:最長10年(据置期間最長5年以内)
融資額や返済期間、利率などはどのような事業を創業するか、申請者の状況などによって変動するため、より細かい情報を知りたいという方は日本政策金融公庫や専門家へ事前に確認しておくと良いでしょう。
日本政策金融公庫の創業融資を無事に受けるためには、次のような準備を入念に行う必要があります。
創業計画書の作成に際しては、第一に創業目的をはっきりとさせ、事業の指針を示すことが求められます。
次に、創業する事業の強みをわかりやすく伝えられるよう、マーケットリサーチなどの結果をもとにした競合に対しての優位性や、ターゲット顧客を詳細に記載します。
さらに、売上や利益の予測を具体的に示した収支計画も策定することで、事業を堅実かつ計画的に経営できる旨も強調します。
このように、創業する事業の実現可能性や持続性が、どういった点にあるのかということを、創業計画書を通してしっかりとアピールすることが大切です。
※創業計画書についての詳細は、こちらの記事もご覧ください。
<創業計画書とは?日本政策金融公庫の創業計画書のポイントを解説>
必要な創業資金の総額に対する自己資金の割合や、その自己資金を準備してきた過程なども創業融資の審査では重要な要素となります。
計画性を持って自己資金を貯蓄してきたという事実は資金を適切に管理できることの証の一つとなり、創業融資の審査で好意的な評価に繋がりやすくなります。
※自己資金の詳細については、こちらの記事もご覧ください。
<自己資金なしで創業融資を受けることはできるのか解説>
クレジットカードや各種ローンの支払いを繰り返し滞納している場合は、創業融資審査において大きなマイナスとなります。
そのため、普段から各種支払いの期日を守るよう意識し、信用情報を良好な状態に保っておくことが重要です。
※信用情報が創業融資にどのような影響を与えるかなど、詳細についてはこちらの記事もご覧ください。
<信用情報とは?創業融資における影響を解説>
創業融資の申請手続きは、次のような流れになります。
1.必要書類(創業計画書、自己資金の証明資料など)の準備
2.申し込み
3.日本政策金融公庫担当者と面談、審査
4.融資決定後、契約手続き
5.融資の実行
創業融資の申し込みを行ってから実際に融資金が着金するまでは、1か月前後要することが一般的ですので、必要なタイミングで融資金を受け取れるよう準備は計画的に進めるようにしましょう。
※日本政策金融公庫の創業融資の流れは、こちらの記事もご覧ください。
<日本政策金融公庫の創業融資の流れを解説>
今回の記事では、運送業を創業したい方に向けて、日本政策金融公庫の創業融資制度について解説しました。
運送業の創業にあたり、創業融資は非常に頼もしい制度であると言えます。
しかし、創業融資の審査を通過し、無事に資金を借り入れるためには創業計画書の作成、自己資金の準備など、事前の段取りが重要です。
創業時の資金調達に懸念事項がある場合は、日本政策金融公庫の無料相談窓口の活用や、創業融資に詳しい専門家に問い合わせることが、成功への糸口となります。
創業融資てづくり専門支援センターでは、4,500件以上の創業融資サポート・創業計画書・事業計画書の作成を支援してきた実績とナレッジに基づき、着手金なしの完全成功報酬(一律固定)で創業融資に関するサポートを提供しております。
資金調達や創業資金に関してのご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

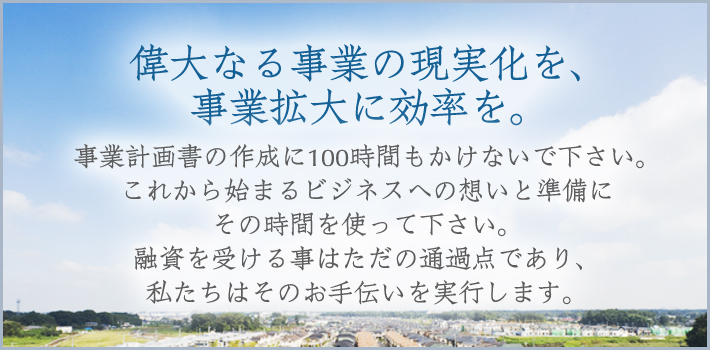
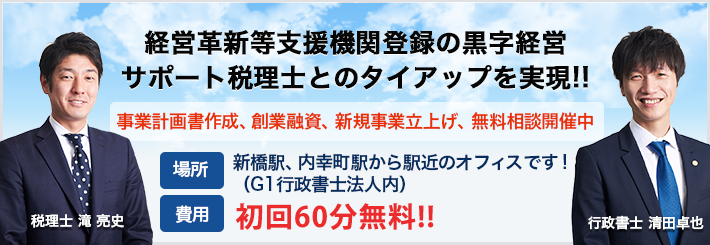
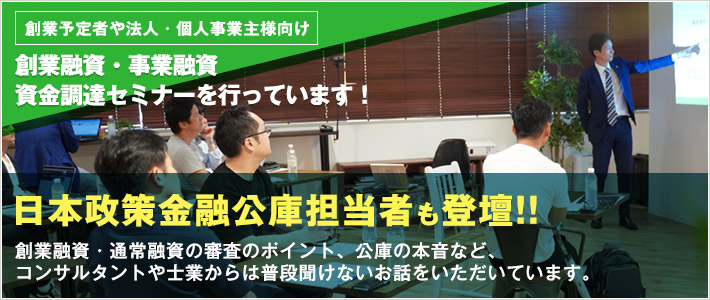



東京本社
〒100-0005
東京都千代田区丸の内1丁目1番1号
パレスビル5階
大阪支社
〒541-0046
大阪府大阪市中央区平野町3-2-8
淀屋橋MIビル3階
TEL / 0120-3981-52
FAX / 03-4333-7567
営業時間 月~土 9:00~20:00
メール問い合わせ 24時間対応

創業融資てづくり専門支援センター長の行政書士清田卓也でございます。
当センターは親切、丁寧、誠実さをモットーに運営しております。
事業計画書の作り方から創業融資まで、起業家・経営者様のほんのちょっとした疑問にもご対応させていただいております。
お気軽にご連絡下さい。