<最終更新日>
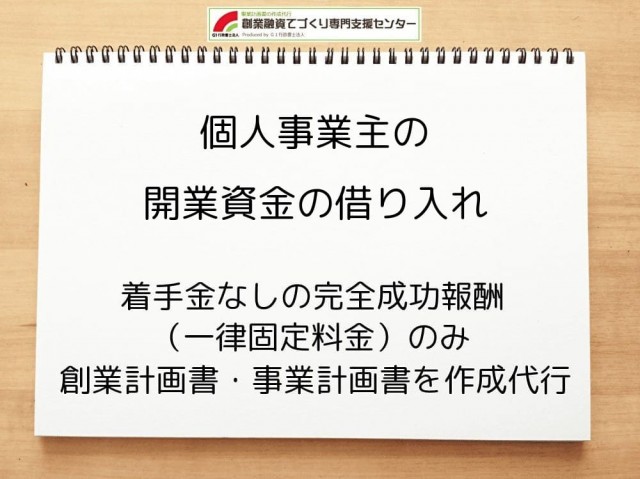 これまで培ってきた経験やスキルを活かし、独立して自分の事業を立ち上げたいと考える方もいるのではないでしょうか。
これまで培ってきた経験やスキルを活かし、独立して自分の事業を立ち上げたいと考える方もいるのではないでしょうか。
そのような方の第一歩として、個人事業主として開業し事業を立ち上げる方も多いですが、その上で避けて通れないのが「開業資金」の問題です。
開業資金の計画をしっかりと立て、事業の土台を築くことができなければ、どんなに素晴らしい事業アイデアがあっても成功の可能性が低くなってしまいます。
そこで本記事では、個人事業主の開業資金について解説していきます。
会社員という働き方が一般的だった時代から、多様な働き方の時代へ変化してきました。
個人事業主という選択もそのひとつであり、自身の裁量でビジネスを展開できるという大きな魅力があります。
個人事業主とは、法人を設立せずに個人で事業を行うことを指します。
会社員として働くよりも、自身のスキルや経験を直接ビジネスに活かせるため、仕事のやりがいや達成感をより強く感じられます。
働く時間や場所を自由に選択できる柔軟性も現代の多様なライフスタイルに合うということで、選択肢として注目されています。
自分のペースで仕事を進めながら、事業の成長が直接収入に結びつく喜びは何物にも代えがたい魅力です。
もちろん、自己管理や責任が求められますが、それが個人事業主としての醍醐味であり、自己成長の機会にもつながります。
個人事業主と法人では、設立手続きや税金、社会的信用度などに大きな違いがあります。
個人事業主は開業届一枚で事業を開始できるのに対し、法人は設立登記が必要であり費用や手間がかかります。
税金面では、個人事業主は所得税と住民税、法人は法人税とその他いくつかの税金が発生しますが、所得額によっては法人の方が税負担は軽くなるケースも出てきます。
社会的な信用度という点では、一般的に法人の方が高いとされています。
また、金融機関からの融資や大手企業との取引では、法人の方が有利に働くことが多いでしょう。
もちろん、個人事業主の場合でも、経験によっては信用を得られる場合もありますが、今後の事業拡大を考えるのであれば、将来的には法人化も視野に入れるべきです。
初期の段階では、個人事業主としてスタートし、事業の成長に合わせて法人化を検討するという方も少なくありません。
それぞれのメリット・デメリットを理解し、事業フェーズに合った形態を選ぶことが大切です。
個人事業主として開業する際、「自己資金だけでなんとかなるだろう」と安易に考えてしまう方もいますが、これは大きなリスクを伴います。
開業資金と一口に言っても、その内訳は多岐にわたります。
漠然と「お金が必要」と考えるのではなく、どのような費用がどれくらい必要なのかを具体的に把握することが、確実な開業資金の計画を立てるための第一歩です。
開業資金は、業種や開業地域によっても違いはありますが、一般的には①初期の費用(イニシャルコスト)、②事業開始後の毎月の費用(ランニングコスト)、③開業資金とは別にご自身の生活費約6~7ヶ月分を計画することが多いです。
初期費用(イニシャルコスト)は、事業を開始する段階で一度だけ発生する費用のことで、設備資金とも言います。
具体的には、店舗や事務所の敷金・礼金、内装工事費、什器・備品の購入費、ウェブサイト制作費、許認可取得費用などが挙げられます。
これらは事業の基盤を作るための重要なものであり、事業内容によっては数百万円、場合によってはそれ以上かかることもあります。
一方、毎月の費用(ランニングコスト)は事業を継続していく上で毎月発生する費用のことで、運転資金とも言います。
具体的には家賃や光熱費、通信費、広告宣伝費、消耗品費、外注費、人件費などが挙げられます。
これらの費用は毎月確実に支払う必要があるため、安定的な売上が上がるようになるまでの期間を考慮し、数ヶ月分の毎月かかる費用(ランニングコスト)を初期費用(イニシャルコスト)にも含めて準備しておくことが重要です。
この二つのコストを正確に見積もることが、資金ショートを防ぎ、事業を維持していくために必要となります。
開業資金の内容は多岐にわたるため、
・店舗取得費用は足りるか
・内装・改装費用は足りるか
・仕入れに必要な費用は足りるか
・事業開始後の広告費用は足りるか
・従業員の人件費は足りるか
・当面の生活費は確保できているか
など、開業準備の際にしっかりと確認することが重要です。
特に個人事業主の場合、事業資金と生活費の境界が曖昧になりがちで、資金計画が厳しくなってしまうケースが多く見受けられます。
開業当初は売上が安定しなかったり、想定よりも事業の立ち上がりに時間がかかることもありますが、その間も、家賃、通信費、消耗品費といった毎月の費用(ランニングコスト)や自身の生活費は発生し続けます。
もし、これらの費用を見誤って資金をギリギリで準備してしまうと、突発的なトラブルや予期せぬ出費が発生した際に、資金ショートしてしまう恐れがあるため、十分に資金を確保しておきたいものです。
目安としては、当初の見積もりよりも1~2割程度多めに資金を準備しておくことをお勧めします。
開業資金の必要額は開業する場所や業種によって大きく変わります。
例えば、店舗を構える小売業や飲食店であれば、物件の取得費用や内装工事費、設備投資など多くの初期費用がかかります。
一方、IT系のコンサルタントやWEBデザイナーの方が自宅を拠点とする事業展開であれば、初期費用は少なく開始することが可能です。
また、都市部で事業を行う場合は、地方に比べて賃料や人件費が高くなる傾向にあるため、同じ事業内容でも必要な開業資金は大きく変わってきます。
このように、ご自身の事業実施場所や事業の特性を具体的に検討し、必要な資金を細かく洗い出して余裕を持った資金準備をすることが大切です。
自己資金だけで開業資金を全て賄うのが理想ではありますが、自己資金のみでは足りない場合は借り入れを検討することも選択肢のひとつです。
ご自身の貯蓄だけで開業資金を全て賄える方はそう多くありません。
事業をスタートした初期の段階では予期せぬ出費も発生しやすく、自己資金で無理に賄おうとする計画は、かえってリスクを高めてしまう可能性があります。
そのような時に検討すべきなのが、外部からの資金調達です。
最も一般的で安定的なのは金融機関からの融資で、返済義務はあるものの、低金利でまとまった資金を調達できる可能性が高い方法といえます。
開業資金を借り入れることに対して、「借金」というネガティブなイメージを持つ方もいらっしゃるかもしれませんが、事業を始める上で資金を借り入れることは決して悪いことではありません。
むしろ、事業を安定させ、成長させるための「賢い選択」であると捉えるべきです。
適切な額の借り入れは、事業の運転資金に余裕を生むため、事業を拡大するために積極的に事業へ集中して取り組むことができるようになります。
また、金融機関から融資を受ける過程では、事業計画書を用意することが多いです。
自身の事業について深く考え、その事業の可能性を客観的な視点から評価してもらう、貴重な機会にもなります。
日本では国の施策として、新しい事業を始める起業家を支援するための手厚い制度が用意されています。
個人事業主としての開業という大きな一歩を踏み出す際に心強い味方となってくれるのが、国の公的機関が提供する「創業融資」です。
開業段階の実績のない事業者への融資はリスクが高いため、民間の金融機関から融資を受けるのは難しい傾向にあります。
しかし、公的機関は起業家支援を目的としているため、比較的融資を受けやすいという特長があります。
公的機関が実施している創業融資は、「新しいビジネスの創出を促し、経済の活性化を図る」という国の狙いがあります。
そのため、低金利で融資が受けられたり、担保や保証人が不要なケースがあったりと、開業を考える事業者にとって心強い存在です。
公的機関はいくつかありますが、創業融資において代表的なものは「日本政策金融公庫」と「信用保証協会」の二つです。
日本政策金融公庫は政府系金融機関であり、民間の金融機関では対応しにくい創業支援や中小企業・小規模事業者支援などを行っています。
一方で信用保証協会は、中小企業が民間の金融機関から融資を受ける際に、「信用保証」を行う機関です。
万が一の際に、信用保証協会が保証をしてくれるため、銀行は融資のリスクを減らすことができ、実績の少ない中小企業や個人事業主の場合でも融資に応じやすくなります。
この二つの機関は、それぞれ異なるアプローチで創業時の支援を行っているため、ご自身の状況や希望する融資の形態に応じて検討するといいでしょう。
日本政策金融公庫は、政府が100%出資している金融機関です。
一般的な銀行が営利を目的としているのに対して、日本政策金融公庫は国の政策に基づき、中小企業・小規模事業者の支援や、創業時の支援を行っています。
日本政策金融公庫は、前述した通り国の政策として起業家の支援を行っています。
そのため、民間の金融機関では難しいとされる、実績のない創業期の事業者に対しても柔軟な姿勢で融資を検討してくれます。
開業後、すぐには安定した売上が見込めない場合でも、日本政策金融公庫の創業融資を活用することで、必要な資金を確保し、事業を円滑に進めることができます。
日本政策金融公庫は、単に資金を融資するだけでなく、事業の成功を後押しするパートナーとなってくれます。
様々な種類の融資から事業フェーズや資金使途に応じた最適なものを提案してくれ、開業前から開業後まで、事業の成長段階に応じたサポートをしてもらえることは大きなメリットといえます。
日本政策金融公庫の担当者は、その計画が実現可能か、将来性があるかを見極め、夢の実現を力強くサポートしてくれます。
信用保証協会は、信用保証協会法(昭和28年8月10日法律第196号)に基づいて設立された公的機関で、直接融資を行うわけではありませんが、民間の金融機関からの融資を円滑にするための橋渡し役となってくれます。
信用保証協会は、中小企業や個人事業主が民間の金融機関から資金を借り入れる際に、公的な保証人となってくれる機関です。
民間の金融機関は実績のない開業段階の事業者への融資には慎重になる傾向があります。
しかし、信用保証協会が保証に入ることで、万が一、事業者が返済できなくなった場合は、信用保証協会が事業者に代わって弁済してくれるため、金融機関は安心して融資を実行できるようになります。
これにより、これまで民間の金融機関から融資を受けることが難しかった事業者も、必要な資金を調達しやすくなります。
信用保証協会を利用する場合は所定の保証料を支払うことになり、この保証料は融資額や保証期間、保証制度によって異なりますが、事業のリスクを軽減し、円滑な資金調達を実現するために必要な経費と考えるといいでしょう。
日本政策金融公庫と信用保証協会は、どちらも創業融資をサポートする公的機関ですが、その役割と利用方法には違いがあります。
日本政策金融公庫が直接融資を行うのに対し、信用保証協会は民間の金融機関からの融資を保証する仕組みです。
どちらを選ぶかは、ご自身の事業状況や資金調達の希望によって変わってきます。
例えば、比較的少額の資金をスピーディーに調達したい場合や、担保・保証人を立てずに融資を受けたい場合は、日本政策金融公庫の創業融資制度が選択肢となるでしょう。
一方、将来的に民間の金融機関との取引を強化したい、あるいは公庫の融資だけでは足りない場合は、信用保証協会の保証付き融資を検討することが有効です。
それぞれの特徴を理解し、ご自身の事業にとって最適な資金調達ルートを選びましょう。
独立して個人事業主として事業を展開したいという目標を実現するためには、情熱やアイデアだけではなく、堅実な資金計画が不可欠です。
個人事業主としての独立はリスクも伴う大きな挑戦と言えます。
しかし、綿密な資金計画を立てることで、そのリスクは軽減され成功への道筋がより明確になります。
自己資金の準備、初期費用と運転資金の正確な見積もり、そして融資制度の積極的な活用。
これら一つ一つのステップを丁寧に進めることが、事業の安定と成長につながっていきます。
資金計画は事業の進捗に合わせて定期的に見直し、必要に応じてブラッシュアップをすることで、自信を持って独立への一歩を踏み出すことができるとともに、その後の事業の安定した継続につながります。
資金計画や融資の申し込みは専門的な知識が求められる場面が多く、一人で全てを完璧にこなすのは簡単ではありません。
そのような時は専門家に相談することをおすすめします。
事業計画書の作成支援、最適な融資制度の選定、金融機関との交渉のサポートなど、多岐にわたるアドバイスが可能です。
専門家の知見を借りることで事業計画の精度を高め、融資審査の通過率を向上させることにも期待できます。
一人で悩みを抱え込まず、積極的に専門家の力を借りることは、事業成功への賢い近道です。
今回は個人事業主の開業資金について解説しました。
個人事業主としての独立は新たなキャリアを築く上で、とても魅力的な選択肢です。
しかし、その夢を実現するためには、情熱やアイデアと同じくらい、堅実な「開業資金」の計画が重要です。
資金調達においては、日本政策金融公庫や信用保証協会といった公的機関の創業融資制度が心強い味方となってくれるでしょう。
当サイトを運営する創業融資てづくり専門支援センターでは、4,500件以上の創業融資サポートや創業計画書・事業計画書の作成支援に携わってきた実績を持ち、その経験や知見を活かして、着手金なしの完全成功報酬(一律固定)にて創業融資をサポートさせていただくことが可能です。
「創業融資に申請したい」「創業計画書や事業計画書の作成をプロにサポートしてほしい」という方は、お気軽にご連絡ください。

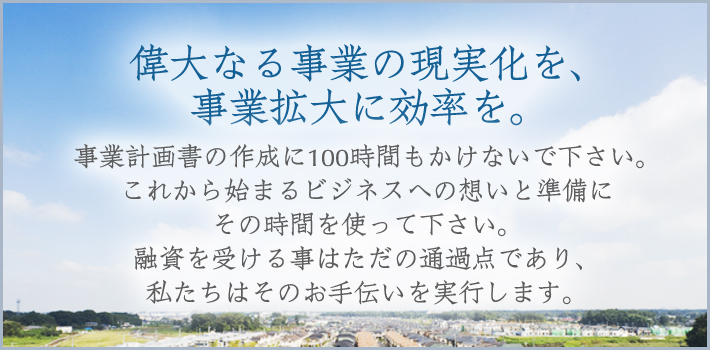
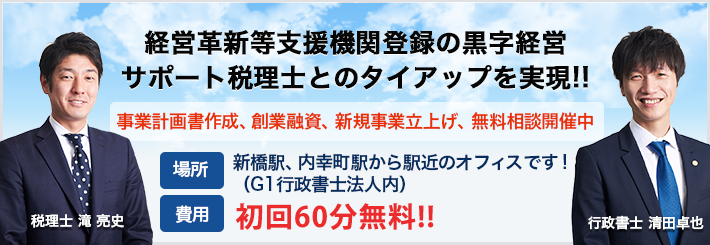
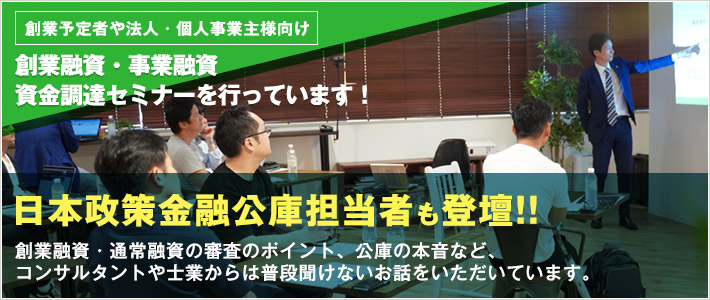



東京本社
〒100-0005
東京都千代田区丸の内1丁目1番1号
パレスビル5階
大阪支社
〒541-0046
大阪府大阪市中央区平野町3-2-8
淀屋橋MIビル3階
TEL / 0120-3981-52
FAX / 03-4333-7567
営業時間 月~土 9:00~20:00
メール問い合わせ 24時間対応

創業融資てづくり専門支援センター長の行政書士清田卓也でございます。
当センターは親切、丁寧、誠実さをモットーに運営しております。
事業計画書の作り方から創業融資まで、起業家・経営者様のほんのちょっとした疑問にもご対応させていただいております。
お気軽にご連絡下さい。