<最終更新日>
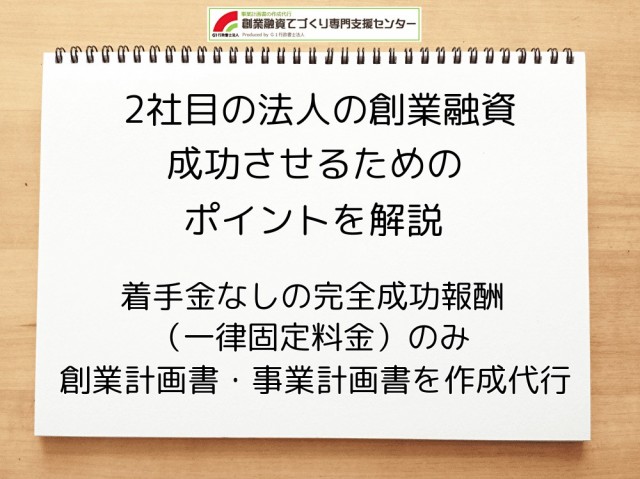
過去に創業融資を受けたことがある創業者様から、
「また新たに法人を立ち上げようと考えているが、2社目も創業融資を受けられるか」
という質問をいただくことがあります。
創業融資は、2社目の法人であっても受けることが可能です。
ただし、1社目の法人の創業融資に比べると気を付けるべきポイントがいくつかあります。
今回は、2社目の法人で創業融資を申し込む場合のポイントや2社目の創業融資を成功させるための対策などについて解説していきます。
2社目の法人で創業融資を申し込む際に気を付けるべきポイントとしては以下が挙げられます。
ポイントの1つ目は、2社目の創業融資の申し込みの際に既存法人(1社目)の財務状況も確認され、審査の結果に関わってくるという点です。
1社目の法人の財務状況が芳しくなかったり、融資審査に落ちている場合は2社目の創業融資も通らない可能性が高まります。
これは、創業融資を提供する日本政策金融公庫や金融機関から「たとえ別法人であったとしても、代表者が同じ場合は関連会社である」と判断されるためです。
金融機関としては、新しい法人(2社目)に貸し出した資金が、融資が下りなかった既存法人に流用されてしまう、いわゆる迂回融資を防ぐ必要があることから、審査においては関連会社の財務情報も精察されます。
関連会社は、創業融資の申し込みに際して作成する「創業計画書」の項目として設置されていますので申告する必要があり、1社目の法人の決算書提出が求められます。
※創業計画書の詳細は以下の記事もご覧ください。
<創業計画書とは?日本政策金融公庫の創業計画書のポイントを解説>
また、1社目のこれまでの収益状況や資金の流れ、債務状況なども入念に確認され、代表者が同一である場合は、その代表者のバックグラウンドや事業成果も重要な判断基準となります。
なお、「1社目の法人の融資が承認されない状況」の例としては、以下のようなものが挙げられます。
■貸借対照表上の負債の合計金額が資産の合計金額を上回っている(債務超過)
■過去の業績やキャッシュフローから融資の返済は厳しいと判断されている
■審査上判断された融資枠の上限まで借り入れをしている
■融資の返済が滞ったことがある
■1社目の法人の関係者の中に、日本政策金融公庫や金融機関から取引不可と判定されている人がいる
2社目の創業融資を申し込む前に、財務資料をアップデートし、適宜事業や財務状況のブラッシュアップを行うようにしましょう。
「新しく2社目の法人を作るのだから、融資枠や限度額もその分増えるのではないか」
とお考えになる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、既存法人と2社目の法人の代表者が同一人物の場合は、法人ごとに融資枠が分けられるのではなく、その代表者単位で一つの融資枠と判断されます。
つまり1社目と2社目の代表者が同じ場合、融資枠は一つとして扱われるため、残念ながら借りられる枠が増えるわけではない、ということになります。
※この融資枠は与信枠とも呼ばれ、法人がその時点で借りることができる最大額を指します。与信枠は制度上で設定されている融資上限額とは別に、その法人ごとの信頼力などに基づいて設定されます。
例えば、日本政策金融公庫の融資枠が1,000万円と判断されている場合、既に1社目で700万円の融資を受けていれば、2社目では300万円を超える融資は受けることはできません。
このような場合、2社目で300万円以上創業融資を受けるためには1社目で受けた融資の残額、すなわち借入残高を減らす必要があります。
1社目も2社目も同じ人が代表者になる場合は、融資枠(与信枠)が一つになる関係上2社目の融資額は必然的に引き下がるという点を念頭に置くようにしましょう。
次に、2社目の法人の創業融資を成功させるための対策などを解説していきます。
まずご紹介したい対策は、2社目の代表者を1社目とは別の人にする、というものです。
前述のとおり、融資における枠は法人単位ではなく代表者ごとに設けられるため、新しい法人の代表者を既存法人とは別の人にすることで、それぞれの法人が別個の事業体であると判断される可能性が高まります。
ただし、1社目の法人の代表者が2社目において主要な株主となる場合、実質的な経営権を1社目の代表者が有しているのではないかと金融機関から疑われる場合があることに注意しなければなりません。
こうしたケースでは、株式の保有割合や役員体制を調整し、既存法人と2社目の法人との分離性をきちんと証明することが、2社目の創業融資成功の鍵となります。
2つ目の対策は、1社目とは別の金融機関に創業融資を申し込むという方法です。
1社目と2社目が関連会社であると見なされるかどうかは、主に金融機関によって判断されます。
そのため1社目とは別の、すなわち既存の取引先ではない金融機関に新たに創業融資を申し込むことで、1社目と関連のある法人と判断される可能性を下げることができます。
しかし、当然ですがこの場合はゼロベースで新規の申し込みを行うということになります。
1社目と同じ金融機関を利用すれば、金融機関側が融資状況を把握しているため、申込作業が簡便になることもありますが、別の金融機関を利用する場合はまたゼロから手続きを行う必要があるということになります。
また、異なる金融機関に申し込んだとしても、1社目と2社目どちらも保証協会付きの融資である場合は、保証協会が両社を一括で審査することになるため、別の金融機関に申し込む効果が無くなることになります。
別の金融機関に申し込むメリットがどれくらいあるか、また既に利用している、あるいはこれから利用する予定の融資が保証協会付きかどうか、自社の状況と併せて検討・考慮していく必要があります。
シンプルなロジックですが、既存法人の借入残高を減らしてから2社目の創業融資を申し込むという方法もあります。
「1社目も2社目も、どうしても同じ代表者しか立てられない」
「それぞれの会社で違う代表者を選んだが、同一会社だと見なされてしまった」
という場合でも、1社目のそもそもの借入残高が減っていれば2社目で借りられる枠が増えるためです。
事業を始めたい、すなわち資金を確保したい時期にもよるところではありますが、2社目の創業が急務ではない場合は、例えば既存法人の2期目の決算が終わってから融資に申し込むという選択肢を検討してみるのも良いかもしれません。
本記事では、創業融資を2社目の法人で申し込む際のポイントや2社目の創業融資を成功させるための対策などについてお伝えいたしました。
「1社目の事業経営で忙しいため、2社目の創業融資申請にあまり時間をかけられない」
「2社目の創業融資申し込みも成功させたい」
という方は、専門家のサポートを受けることも有効な選択肢のひとつになりますので、検討をおすすめします。
創業融資てづくり専門支援センターでは、累計4,500件以上の創業融資サポート・創業計画書・事業計画書の作成実績を記録しており、これまで積み上げてきた知見やナレッジに基づき、着手金なしの完全成功報酬(一律固定料金)にてサポートを提供しています。
創業融資の申し込みにあたって専門家の手を借りたい方や、資金調達や開業資金の確保を効率的に行いたい方は、ぜひお気兼ねなくご連絡ください。

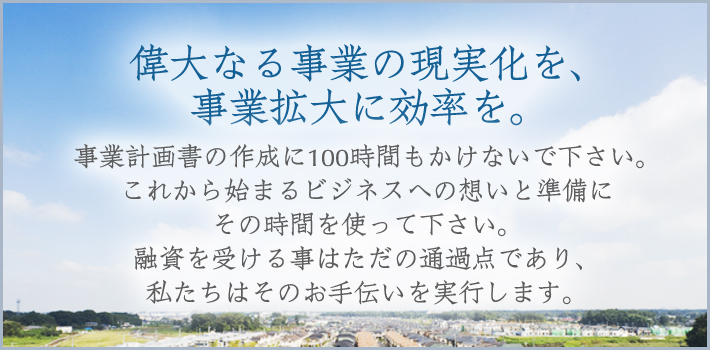
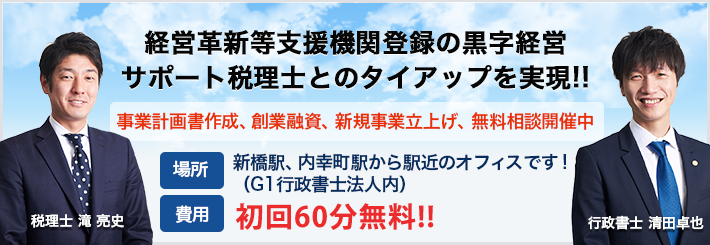
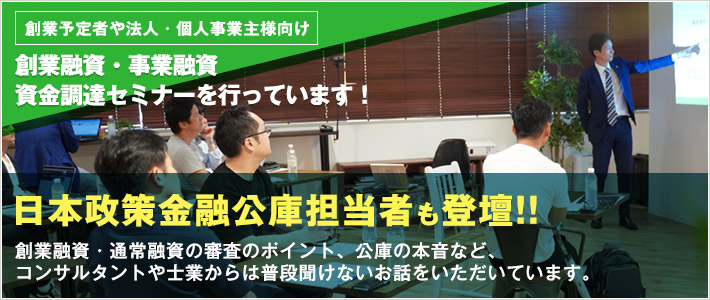



東京本社
〒100-0005
東京都千代田区丸の内1丁目1番1号
パレスビル5階
大阪支社
〒541-0046
大阪府大阪市中央区平野町3-2-8
淀屋橋MIビル3階
TEL / 0120-3981-52
FAX / 03-4333-7567
営業時間 月~土 9:00~20:00
メール問い合わせ 24時間対応

創業融資てづくり専門支援センター長の行政書士清田卓也でございます。
当センターは親切、丁寧、誠実さをモットーに運営しております。
事業計画書の作り方から創業融資まで、起業家・経営者様のほんのちょっとした疑問にもご対応させていただいております。
お気軽にご連絡下さい。