<最終更新日>
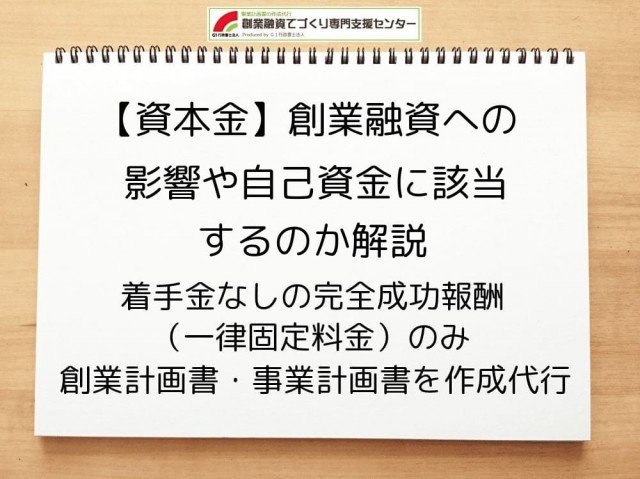
株式会社や合同会社などの営利法人を設立する場合は資本金を設定する必要がありますが、創業融資を活用しようと考えている方の中には、創業融資の審査で資本金額は影響するのかという疑問を持った方もいるのではないでしょうか。
この記事では、資本金についての概要や創業融資における影響、自己資金に該当するかなどを解説していきます。
資本金とは、株式会社や合同会社などの営利法人を設立する際に、出資者である株主から出資される資金となり、創業時の運転資金や設備資金に充当できます。
また、自由に使用できるため、資本金の額と会社の手元資金は必ずしも一致するわけではありません。
資本金は会社の信頼度を表す一つの目安となるため、創業時には資本金を多くすること、または少なくすることそれぞれのメリットとデメリットをよく考慮した上で、その金額を決めることが大切です。
創業融資における自己資金は、起業や創業する事業に使う予定の自分のお金となり、現預金や貯金、退職金などが該当します。
逆に家族や親族、金融機関から借りたお金などの返済をしなければいけない資金は自己資金には該当しません。
資本金は株主から出資してもらう資金ですが、返済の必要はなく創業後の事業で使用するための元手資金であることから、創業融資においては自己資金として考慮できる可能性が高い資金です。
資本金の扱いについては、金融機関や創業融資サポートを受ける専門家へ事前に確認しておきましょう。
※創業融資における自己資金の詳細は、以下の記事もご覧ください。
<自己資金なしで創業融資を受けることはできるのか行政書士が解説>
資本金は創業融資においても重要視されているポイントになります。
これは、資本金の額が多い会社は創業後に使用できる資金が多いということになるため、計画書通りに経営することができると見なされて、創業融資の審査でプラスに評価される傾向があるためです。
それでは、創業時の資本金はいくらに設定するべきでしょうか。
資本金の額を決めるにあたって、まずは資本金が少ない場合と多い場合のメリット・デメリットをそれぞれ把握しておきましょう。
■メリット
・会社設立の費用負担を抑えて創業できる
・節税効果を享受することができる
■デメリット
資本金があまりにも少ない場合、会社としての信用力が低くなり、「創業融資をはじめとした融資審査に通過しにくくなる恐れがある」「法人口座の開設を行えない場合がある」といった弊害が生じる可能性がある
■メリット
・創業融資などの審査通過率が高まる可能性がある
・経営破綻や資金ショートのリスクが低いと見なされやすく、クライアントや取引先との信用を得やすくなる
■デメリット
・会社創業後2年間は消費税の免税措置があるが、資本金が1,000万円以上の場合は当該措置の対象外となる
・会社の利益に関わらず納税義務のある法人住民税の均等割部分は、資本金額と従業員数で決まるため法人住民税が高くなる
法律的な観点で言えば、資本金は最低1円からでも会社を設立できます。
さらに、日本政策金融公庫の創業融資「新規開業・スタートアップ支援資金」においても、資本金の額は要件に定められていません。
しかし、前述したとおり資本金が過度に少ない場合は、創業融資の審査に通りづらくなったり、銀行口座の開設ができなくなったりする可能性があります。
資本金をいくらにしようか決めかねている方は、メリット・デメリットなども念頭に置いたうえで資本金の額を検討することをおすすめします。
また、創業融資の審査を通過できるかは資本金はもちろんですが、申請者のその他の様々な情報を踏まえて判断されますので、創業融資を利用したいと考えている場合はこの点も認識しておきましょう。
資本金はいくつかのポイントがありますので、そちらについて解説します。
借り入れた資金を資本金に含めることは認められていません。
前述したとおり、資本金の額は融資等の審査における信用力に影響を与えるため、借入金を資本金に含めることはいわゆる「見せ金」と同様になり不正行為になります。
また、借入金は貸借対照表上の負債の部に計上され、資本金は純資産の部に計上されることとなるため、お金としての質も全く違うものです。
そのため、日本政策金融公庫をはじめとした金融機関は、融資審査において資本金の内容も確認します。
資本金は返済義務のない自己資金や適法な出資で準備しましょう。
※会社が役員から借り入れた資金を資本金に転換する「DES(デット・エクイティ・スワップ)」という方法は認められています。
資本金はその額を設定した後も、会社の運営や事業の強化など、経営において必要な用途で使用することが可能です。
会社を創業される方の中には、「資金繰りに際して資本金を使用してはいけない」と誤解されている方もいらっしゃいますが、むしろ資本金を有効に活用して、更なる利益に繋げていくことが重要であることを念頭に置いて、資本金額を決めるようにすると良いでしょう。
会社を設立する際に、創業者以外の第三者から出資を受けることもありますが、この場合は出資者に対して出資額に応じた株式を引き渡す必要があります。
この際、創業者よりも多くの株を持つことになる出資者がいると、当該出資者の議決権割合のほうが高くなってしまう可能性があります。
議決権は、株主総会で経営方針や重要事項を決める際の投票権のようなもので、原則として持っている株式の数によって票数が決まります。
すなわち、株式の多い人ほど会社経営に影響力を持つということです。
これにより、せっかく会社を創業しても、株式の比率次第では創業者自身が思うような経営をできなくなる可能性があります。
また、代表を含めた役員の解任も出席要件を満たした株主総会で出席している議決権の過半数(状況により2/3)で決議できるため、自分が過半数の議決権を持っていない場合は、他の株主によって代表の立場を失うことになる可能性すらあります。
このため、複数人が出資する場合は、自分自身で最低でも過半数、可能であれば2/3以上の議決権を保てるようにするなど、株式の配分には注意する必要があります。
本記事では、資本金についての概要や創業融資における影響、自己資金に該当するかなどについて解説しました。
資本金は創業融資の審査においても重要なポイントとなりますので、ぜひ今回解説した内容も考慮して資本金はいくらにするかを検討していただければと思います。
創業融資てづくり専門支援センターでは、累計4,500件を超える創業融資支援や創業計画書・事業計画書作成のサポートを提供してきた実績と知見を活かして、着手金不要かつ完全成功報酬制(一律固定料金)で支援させていただくことが可能です。
創業融資の利用を考えている方は、どなた様もお気軽にご相談ください。

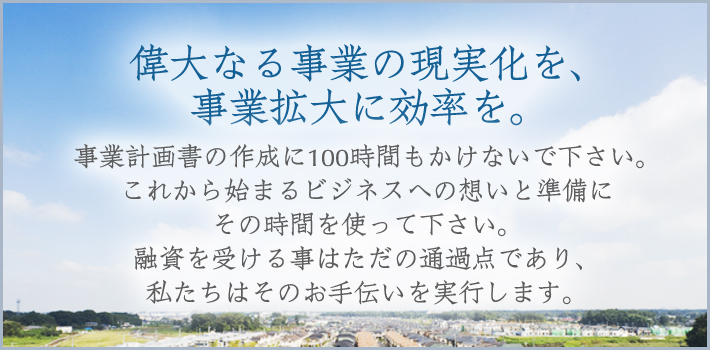
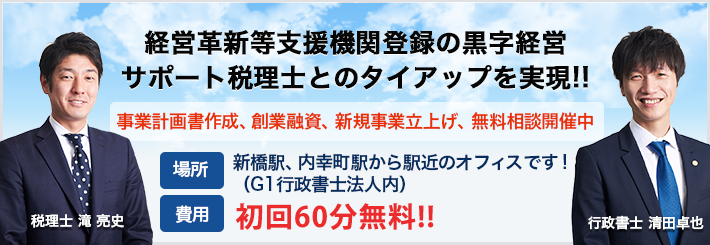
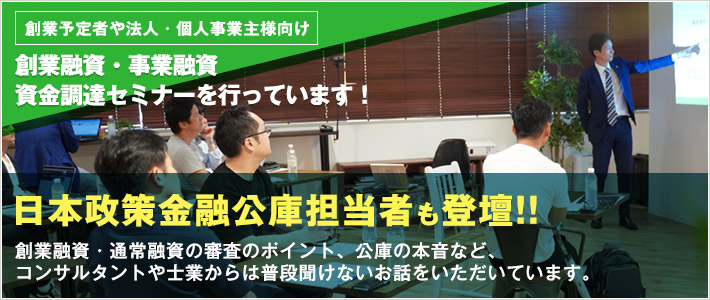



東京本社
〒100-0005
東京都千代田区丸の内1丁目1番1号
パレスビル5階
大阪支社
〒541-0046
大阪府大阪市中央区平野町3-2-8
淀屋橋MIビル3階
TEL / 0120-3981-52
FAX / 03-4333-7567
営業時間 月~土 9:00~20:00
メール問い合わせ 24時間対応

創業融資てづくり専門支援センター長の行政書士清田卓也でございます。
当センターは親切、丁寧、誠実さをモットーに運営しております。
事業計画書の作り方から創業融資まで、起業家・経営者様のほんのちょっとした疑問にもご対応させていただいております。
お気軽にご連絡下さい。