<最終更新日>
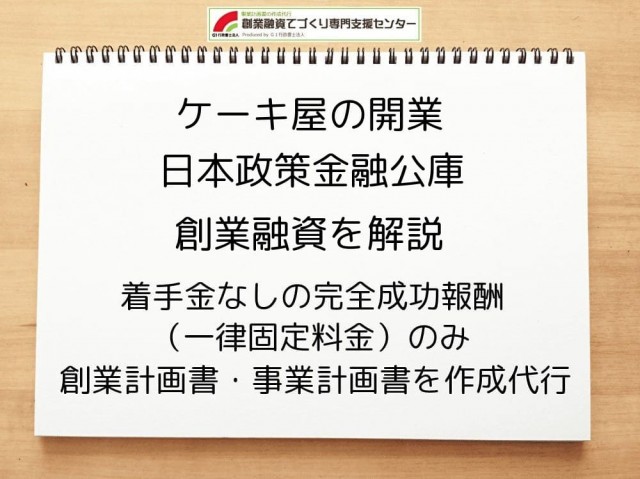
ケーキ屋の創業・開業を目指す方にとって資金調達をどのように行うかは重要な課題の一つです。
店舗物件取得費やケーキ作りに必要な設備や機材の購入費用、創業後数か月分の運転資金など、創業・開業段階にはある程度の資金が必要となりますが、その全額を自己資金のみで補填することは多くの方にとって容易ではありません。
このような時に役立つのが、日本政策金融公庫の創業融資制度です。
創業融資はこれから事業を始める人向けの制度となっており、無担保・無保証で金利が低く、返済期間も長めに設定されているのが特徴です。
この記事では、ケーキ屋の創業・開業を目指している方々に向けて、日本政策金融公庫の創業融資について解説していきます。
日本政策金融公庫は、政府が100%出資する政府系金融機関として、様々な資金ニーズに応えるための融資制度を提供しています。
特に、創業・開業段階の方もしくは創業後間もない方に対しては、無担保・無保証で利用できる創業融資制度を提供しており、ケーキ屋をはじめとした創業時の資金調達手段として多くの方から選ばれています。
■新規開業・スタートアップ支援資金(新規開業資金):無担保かつ無保証人で借りられる創業融資
■生活衛生新企業育成資金:飲食業・理容業・美容業などの生活衛生関係営業者が利用できる融資制度
いずれも、これから創業される方または創業からおおむね7年以内の方が利用対象となっています。
ケーキ屋の創業にあたって創業融資を申し込むには「創業計画書」の作成、提出が必要になります。
創業計画書は念入りな準備と情報整理に加え、内容に整合性と実現性があることが求められます。
以下のポイントを押さえて創業計画書を作成しましょう。
創業の動機を記載する欄では、ケーキ屋を創業したいと思った理由や、その目的を述べていきます。
ただの気持ちや動機を記載するのではなく、これまで積み上げてきた経験やスキル、自分だからこそ出せる強み、そしてその上でどういったお店にしていきたいのかをしっかりと伝えることが大切です。
また、創業に向けて取り組んできた準備の内容や運営方針、見込・既存両方の顧客が存在すること、ならび出店地を選定した理由なども記載していきます。
さらにマネジメント経験や人材育成の実績がある場合は、その旨も構成に加えることで、事業の実現性をより強くアピールできます。
高校や専門学校を卒業した年月日や勤務先、勤続年数といった基本的な情報と併せ、勤務中に担当した業務内容や必要なスキル、役職なども記載しましょう。
また、コンテストで入賞経験などがあれば、その旨も記しておくことで自分が持つ知識や技術をより効果的にアピールすることができます。
販売していく商品の内容やその価格、他店と差別化できる点(強み)、販売戦略などを具体的に記載し、自店の理念やターゲット顧客層をしっかりと伝えられるようにする必要があります。
「他社よりもお手頃価格で販売できる」「厳選した素材を使用している」「ケーキの見た目にこだわっている」など、どういった点が強みとなるかは事業者ごとに異なりますので、自店の場合のセールスポイントを詳細に記載するようにしましょう。
「取引先・取引関係等」の項目には、例えばケーキやスイーツ作りに使う材料の仕入れ先などを記入します。
仕入れ先が知り合いの会社であったり、過去の勤務先で担当した取引先などの場合は、その関係性も記載しておくことで、より信頼度を高めることができます。
仕入れ先が未定の状態だと、ケーキ屋としての事業を始める準備が十分でないと見なされる恐れもあるため、創業融資の申し込みまでに仕入れ先を決めておくようにしましょう。
また、ケーキ屋のような一般消費者が主な販売ターゲットの業種は、この項目にターゲット層や集客根拠、販売戦略なども記載しておくようにしましょう。
「必要な資金と調達方法」の欄は、創業計画書の中でも特に重要な項目の一つです。
創業に必要となる資金(設備資金・運転資金)の総額、およびその資金をどういった方法で調達するのかを明記します。
設備資金に関しては、単価が10万円を超えるものについては必ず見積書を準備し、見積先の名称と具体的な金額を記載します。
また、運転資金に関しても、根拠があいまいな金額で記載はせず、業界の相場データや事業計画をもとにした妥当性のある金額を記載することが重要です。
加えて、創業融資の審査では自己資金の比率が極めて重要なポイントとなり、自己資金をどれだけ準備しているか記入する欄(調達の方法項目内)があります。
自己資金は十分な額を確保しておくよう心がけましょう。
「事業の見通し」は、将来の収支予測の項目となり、「創業当初」と「1年後(もしくは事業が軌道に乗る時期)」2種類の「売上高」「原価」「経費」「利益」などを月平均で記入していきます。
ここで押さえておきたいのは、それぞれの数値に裏付けとなる根拠を持たせ、併せてその算出方法(計算式)を明示することです
売上高の見通しに実現性がなかったり、経費が相場と著しく異なっていたりすると事業計画の信頼性が損なわれ、審査に悪影響を及ぼす恐れがありますので注意が必要です。
■食品衛生責任者
ケーキ屋を創業するためには、「食品衛生責任者」の資格が必須です。
これは、食品衛生法により「食品の製造や販売を行う店舗には、食品衛生責任者の資格を持つ者を1名以上配置しなければならない」と義務づけられているためです。
この資格がなければケーキ屋の営業許可が下りず、創業できません。
各都道府県の保健所で講習を受けることで取得できますので、必ず取得するようにしましょう。
また、食品衛生責任者は必ずしも代表となる人が取得しなければならないわけではありませんので、従業員などが資格を取得しても構いませんが、その人が退職した際に適切な変更手続きを行っていないと、営業許可が取り消されてしまう恐れもあります。
こうしたリスクを避けるため、なるべく代表者自身が食品衛生責任者の資格を取得することが望ましいでしょう。
■防火管理者
防火管理者は、火災の予防や防火体制の整備を担う責任者のことを言います。
収容人員(従業員も含める)が30人を超える飲食店を創業する場合は防火管理者の取得が必須になります。
防火管理者には2つの種類があり、お店の延面積が300㎡以上なら「甲種防火管理者」、300㎡未満なら「乙種防火管理者」を選任しなければいけません。
資格の取得は、地域の消防署などが行う講習を受講する必要があります。
■飲食店営業許可証
飲食店の開業は、各自治体の保健所で「飲食店営業許可証」を取得することが求められます。
営業許可証を取得するためには、「食品衛生責任者の資格保有者がいること」と、「店舗の設備が基準を満たしていること」の2つの要件をクリアしていなければなりません。
設備については、キッチンや客席などの詳細を記した図面を提出し、保健所の職員による実地調査に合格する必要があります。
また、申請者が過去に食品衛生法違反や営業許可取り消しなどの処分歴がある場合、一定期間は飲食店営業許可を申請することができませんので注意しましょう。
ケーキ屋においては、店内にイートインスペースを設けずテイクアウト販売のみに限定する場合は、飲食店営業許可証は不要です。
■菓子製造業許可証
「菓子製造業許可証」は、パンやケーキ、飴などの菓子類を店内で製造・販売する際に必要な許可証になります。
こちらも保健所で申請する必要があり、製造施設や包装作業エリアが所定の条件をクリアしていることが求められます。
日本政策金融公庫の創業融資に申し込むには、以下の条件を満たしていることが求められます。
■創業前または創業後おおむね7年以内であること
■創業計画書(事業計画書)を作成し、その内容を面談で説明できること
■公共料金やクレジットカード、ローンの支払い実績が良好な状態にあること
また、自己資金をどれくらい準備できているかといった点や、創業計画書の記載内容なども創業融資審査において大切なポイントになります。
<融資額の条件>
■新規開業・スタートアップ支援資金:設備資金は最大2,400万円、運転資金は最大4,800万円まで
■生活衛生新企業育成資金:振興計画認定組合の組合員は設備資金最大7億2,000万円まで、運転資金は5,700万円まで、組合員ではない方は設備資金 4億8,000万円まで
※振興計画認定組合の組合員でない場合、原則運転資金を利用することは出来ません。
<返済期間の条件>
返済期間については、どちらの融資の場合も以下の要件になっています。
■設備資金:最長20年(据置期間最長5年以内)
■運転資金:最長10年(据置期間最長5年以内)
融資金額や返済期間、利率などは、実施する事業の計画や申し込む人の状況によっても異なるため、詳細については日本政策金融公庫や各種専門家などにあらかじめ確認しましょう。
日本政策金融公庫の創業融資を成功させるためには、万全の準備が必要です。
■創業計画書(事業計画書)の作成
創業計画書では、まず創業の目的を明らかにし、事業の方針を示すことが求められます。
次に、創業する事業の強みが明確になるよう、市場調査などの結果を踏まえた競合に対しての独自性や、ターゲットとなる顧客層を具体的に記載します。
さらに、売上や利益の展望を詳しく示した収支計画を練ることで、事業経営の安定性や計画性も強調します。
このように、創業計画書の内容を通じて創業する事業の実現性と継続的な成長を支える基盤について、しっかりとアピールすることが重要です。
※創業計画書の詳細は、こちらの記事もご覧ください。
<創業計画書とは?日本政策金融公庫の創業計画書のポイントを解説>
■自己資金の準備
創業融資の審査では、創業にあたり必要な資金の総額に対する自己資金の割合や、自己資金をどのように準備してきたかも重要な材料となります。
自己資金を計画的に貯めてきたことは資金管理をきちんと行えることの証の一つとなり、創業融資の審査でプラスに評価されやすくなります。
※自己資金の詳細は、こちらの記事もご覧ください。
<自己資金なしで創業融資を受けることはできるのか解説!>
■信用情報に傷をつけない
クレジットカードや各種ローンの支払いに常習的な延滞があると、融資審査で不利になる可能性が高いです。
そのため、創業前から支払い管理を徹底し、信用情報を良好な状態に保つことが大切です。
信用情報の詳細はこちらの記事もご覧ください。
<信用情報とは?創業融資における影響を解説>
創業融資は以下の流れで進めていきます。
1.必要書類の準備(創業計画書、資金計画書、自己資金の証明資料など)
2.申し込み
3.日本政策金融公庫担当者との面談、審査
4.融資決定・契約手続き
5.融資実行
創業融資の申し込みから融資が実行されるまでは、1か月前後かかるケースが多いため、創業スケジュールを念頭に置きながら準備を進めるようにしましょう。
※日本政策金融公庫の創業融資の流れは、こちらの記事もご覧ください。
<日本政策金融公庫の創業融資の流れを解説>
今回の記事では、ケーキ屋を創業・開業したい方に向けて、日本政策金融公庫の創業融資制度を解説しました。
ケーキ屋を創業するにあたり、創業融資は非常に頼もしい制度です。
ただし、創業融資を受けるためには創業計画書の作成、自己資金の用意など、事前の準備をしっかりと行うことが重要です。
創業時の資金調達に懸念がある場合は、日本政策金融公庫の無料相談窓口に問い合わせたり、創業融資サポートを行っている専門家のサポートを活用することが成功のポイントとなります。
創業融資てづくり専門支援センターは4,500件以上の創業融資サポート・創業計画書・事業計画書の作成実績を有し、これまで積み上げてきた経験と知見を活かして、着手金なしの完全成功報酬(一律固定)で対応させていただくことが可能です。
資金調達や開業資金でお悩みの方は、ご遠慮なくお問い合わせください。

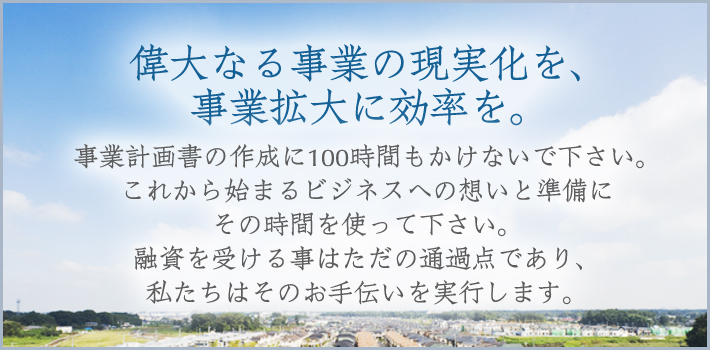
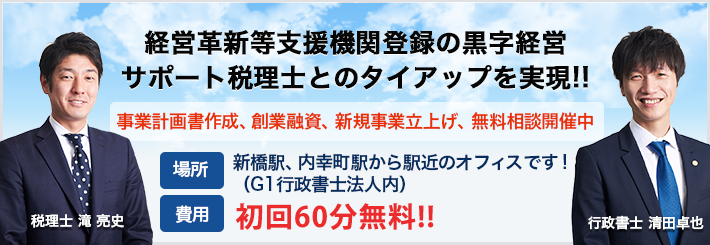
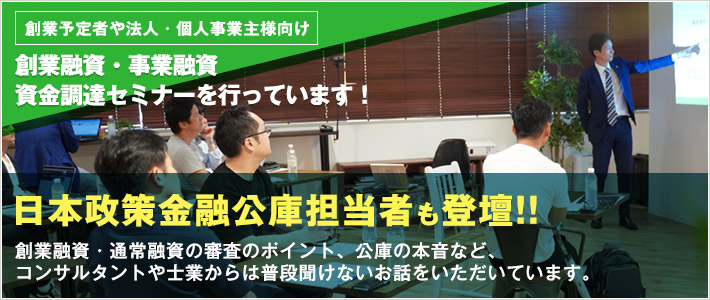



東京本社
〒100-0005
東京都千代田区丸の内1丁目1番1号
パレスビル5階
大阪支社
〒541-0046
大阪府大阪市中央区平野町3-2-8
淀屋橋MIビル3階
TEL / 0120-3981-52
FAX / 03-4333-7567
営業時間 月~土 9:00~20:00
メール問い合わせ 24時間対応

創業融資てづくり専門支援センター長の行政書士清田卓也でございます。
当センターは親切、丁寧、誠実さをモットーに運営しております。
事業計画書の作り方から創業融資まで、起業家・経営者様のほんのちょっとした疑問にもご対応させていただいております。
お気軽にご連絡下さい。