<最終更新日>
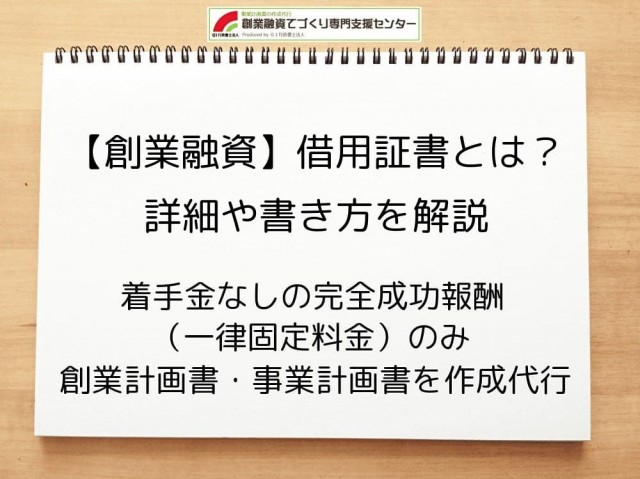 日本政策金融公庫の創業融資は、無事に審査を通過した後もいくつかの手続きが必要となり、そのうちの一つに「借用証書の提出」があります。
日本政策金融公庫の創業融資は、無事に審査を通過した後もいくつかの手続きが必要となり、そのうちの一つに「借用証書の提出」があります。
今回は、日本政策金融公庫の創業融資における借用証書とはどのようなものなのか、詳細や書き方について解説します。
借用証書とは、日本政策金融公庫をはじめとした金融機関から資金を借り入れることを証明するための書類です。
借用証書の作成により借入日や融資金額、返済期間などの契約条件が明文化され、借用証書を金銭貸借の法的な裏付けとすることができます。
借用証書は創業融資の審査に通った後、申込者である借主宛てに郵送されます。
借主が所定の項目に記入のうえ、提出した借用証書が日本政策金融公庫に受理されることで、契約(創業融資)が完了する運びとなります。
ただし、オンラインでの手続きサービス(日本公庫電子契約サービス)を利用した場合は、借用証書は郵送されず代わりに「電子契約手続きのお願い」というメールが届き、そちらに記載のURLから契約内容を確認のうえ手続きを進める流れとなります。
借用証書を記入する前に、以下の対応をしておくようにしましょう。
借用証書は、まずは内容をきちんと確認しましょう。
融資金額や利率、元金や利息の支払方法など、契約内容は借主ごとに異なりますので、自分が申し込んだ内容と相違が無いか記入前にチェックすることが大切です。
借用証書の記入をスムーズに進めるためにも、必要なものはあらかじめ準備しておくようにしましょう。
日本政策金融公庫のホームページでも、記入の前に以下のものを準備するよう推奨しています。
●ペン(消せないもの)
●実印
●収入印紙
●印鑑証明書
●融資金の受取口座の預金通帳
<実印>
個人事業主の場合はその本人の実印を、法人の場合はその法人の実印を用意します。
連帯保証人を付ける場合は、連帯保証人の実印も必要になります。
<収入印紙>
借用証書の左上に書いてある金額のものを用意します。
収入印紙は郵便局やコンビニ、法務局などで購入可能ですが、コンビニの場合は基本的に200円の収入印紙しか販売していない点に注意が必要です。
また、収入印紙の金額は融資額によって異なり、具体的には以下のように定められています。
●100万円を超え500万円以下:収入印紙2,000円
●500万円を超え1,000万円以下:収入印紙10,000円
●1,000万円を超え5,000万円以下:収入印紙20,000円
なお、収入印紙を貼るスペースは1枚分のみとなっているため、例えば2,000円の収入印紙を貼り付けたい場合、「1,000円分の収入印紙を2枚貼る」といったように複数枚の収入印紙を貼ることは控えるようにしましょう。
<印鑑証明書>
融資日から3か月以内の印鑑証明書が必要です。
法人の場合は法務局の窓口や郵送、オンライン申請などで取得することができ、個人事業主の場合は市区町村の窓口などで取得することが可能です。
また、連帯保証人が付く場合は、連帯保証人の分も印鑑証明書の提出が求められます。
<融資金の受取口座の預金通帳>
融資金を受け取る口座の預金通帳も用意しておきます。
必ず、借主本人名義の口座の預金通帳を準備しておくようにしましょう。
ここからは、借用証書の書き方を解説していきます。
※日本政策金融公庫のホームページ「契約書類の記入ガイド」にて動画での説明もありますので、そちらも併せてご参照ください。
最初に、借用証書左下の欄への署名と、実印の押印を行います。
①借用証書と一緒に送られてくる「ご契約に関する重要なご案内」を確認し、内容をきちんと理解した後に、署名欄の上のチェックボックスにチェックを入れます。
②次に署名欄に署名を行います。
印鑑証明書通りの記入が必要となり、法人の場合は法人名と併せて代表者役職と代表者名も記入する必要があります。
例:「○○株式会社 代表取締役 A田B子」
また、法人は署名の代わりにゴム印を利用することも可能です。
個人事業主の場合は、ゴム印の使用は認められませんので注意しましょう。
③署名が完了したら、実印を押印します。
この際、印影が薄くなってしまった場合などは、署名欄の枠内に押印し直してください。
④書類左上の収入印紙の下の欄に実印を押すスペースがありますので、捨印として押印します。
ここまでで、署名・実印の押印は完了です。
連帯保証人がいる場合は、連帯保証人の方にも上記①~④を同じように行っていただきましょう。
事前に用意しておいた収入印紙を貼ります。
収入印紙を貼った後は、借主の実印を消印として押してください。
あらかじめ準備しておいた預金通帳を確認しながら、送金依頼欄を記入します。
なお、借用証書を日本政策金融公庫に提出する際、郵送で提出する場合は当該預金通帳の「表紙」と「見開き1ページ目(口座名義や口座番号などの情報が載っているページ)」のコピーを同封する必要があります。
一方、借用証書を支店の窓口に直接提出する場合は、当該預金通帳の原本が必要となりますので念頭に置いておきましょう。
借用証書に記入する内容は以上です。
借用証書の記入欄を全て埋め終わったら、記入した内容を今一度確認します。
特に以下の項目は漏れの多い箇所となりますので、よく見直しましょう。
●署名欄の上のチェックボックスにチェックが入っているか(連帯保証人がいる場合はその分も確認しましょう)
●署名欄と捨印欄に実印が押印されているか
●収入印紙に消印として実印が押印されているか
借用証書を記入した後は、その他の必要書類と併せて日本政策金融公庫に返送するか、もしくは窓口まで書類一式を持参するか、いずれかの方法で提出します。
郵送の場合は「日本政策金融公庫の窓口まで足を運ぶ手間が不要になる」、窓口まで持参する場合は「郵便が到着するまでの所要時間を省略することができる」というメリットがそれぞれありますので、自身の状況に合わせてどちらかで提出してください。
借用証書をはじめとした書類を提出した後は、おおよそ4営業日前後で創業融資が実行され、融資金が着金する流れとなります。
ただし、借用証書はもちろん他の書類に漏れや不備があった場合などは着金が遅くなりますので、書類を提出する際は正しく記入されているか、抜けのないよう作成、準備を進める必要があります。
本記事では、創業融資の審査を通過した後に提出が必要となる借用証書に関して、その詳細や書き方などを解説しました。
借用証書は創業融資を受け取るために必須となる書類ですので、今回解説したポイントを踏まえて、借用証書を記入してください。
当サイトを運営する創業融資てづくり専門支援センターでは、これまで数々の創業融資サポート・創業計画書・事業計画書の作成をサポートしてきた実績を有し、その件数は4,500件を超えています。
豊富な実績に裏打ちされた経験とノウハウをもとに、着手金なしの完全成功報酬(一律固定)にてご対応させていただくことができますので、「創業融資に申請してみたい!」「創業計画書や事業計画書の作成を、専門家にフォローしてもらいたい」とお考えの方は、お気軽にご相談ください。

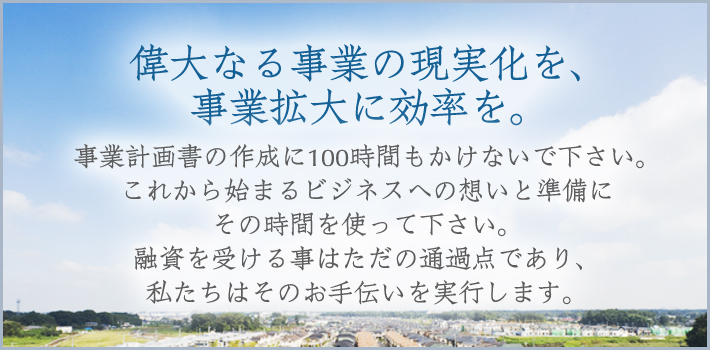
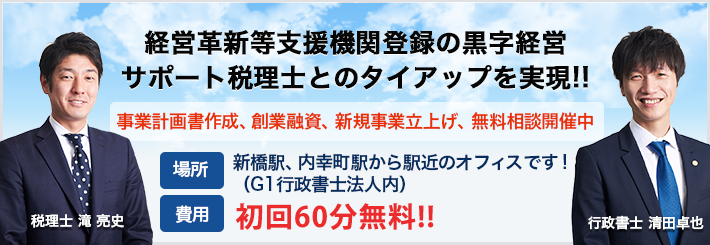
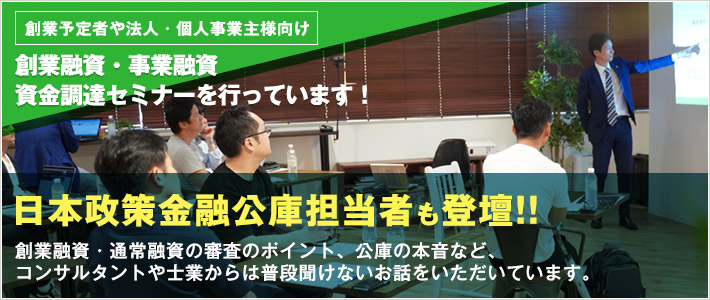



東京本社
〒100-0005
東京都千代田区丸の内1丁目1番1号
パレスビル5階
大阪支社
〒541-0046
大阪府大阪市中央区平野町3-2-8
淀屋橋MIビル3階
TEL / 0120-3981-52
FAX / 03-4333-7567
営業時間 月~土 9:00~20:00
メール問い合わせ 24時間対応

創業融資てづくり専門支援センター長の行政書士清田卓也でございます。
当センターは親切、丁寧、誠実さをモットーに運営しております。
事業計画書の作り方から創業融資まで、起業家・経営者様のほんのちょっとした疑問にもご対応させていただいております。
お気軽にご連絡下さい。