<最終更新日>
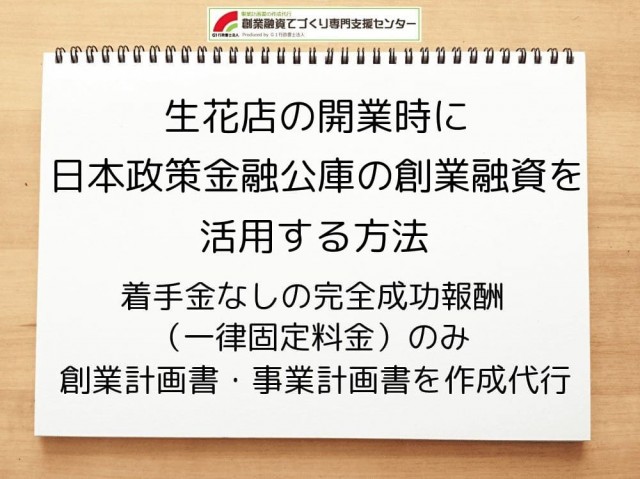 生花店を創業・開業する際、物件取得費用や内装・外構の工事費、創業後にかかる運転資金など、多額の資金が必要になりますが、このような時に活用いただきたいのが「日本政策金融公庫の創業融資制度」です。
生花店を創業・開業する際、物件取得費用や内装・外構の工事費、創業後にかかる運転資金など、多額の資金が必要になりますが、このような時に活用いただきたいのが「日本政策金融公庫の創業融資制度」です。
創業融資はこれから創業・開業しようとしている方が主な対象であり、無担保・無保証で申し込むことができる点が魅力です。
この記事では、生花店の創業・開業を計画している方々に向けて、日本政策金融公庫の創業融資について解説していきたいと思います。
日本政策金融公庫は、様々な資金ニーズに対しての融資制度を提供している政府系の金融機関です。
中でも創業・開業段階の方もしくは創業から日が浅い方に対しては「創業融資制度」を展開しており、創業時の有効な資金調達手段として生花店をはじめ多くの人から利用されています。
日本政策金融公庫では、創業融資「新規開業・スタートアップ支援資金(新規開業資金)」が生花店の創業時に利用されています。
この制度は無担保・無保証で借りることができるという点が大きな特徴で、利用対象となるのはこれから事業を開始する方、または事業開始後おおむね7年以内の方となります。
生花店創業時に創業融資を申し込むためには、「創業計画書」を提出する必要があります。
創業計画書は事前準備と情報の整理をきちんと行って、内容に整合性がある実現可能な計画で作成することが大切ですので、以下の要点を押さえるようにしましょう。
創業の動機欄には、生花店の創業を目指すに至った経緯や目的を記載します。
この際、ただ単に創業したい理由や動機を書いていくのではなく、これまでに得た経験や資格など、自分の強みはどういったところにあって、そしてそれらをお店にどう反映していきたいのかを強調することが大切です。
また、創業のためにどのような取り組みや準備をしてきたか、経営プラン、見込み客や既存顧客が存在すること、および出店する予定の場所を選んだ理由なども併記するようにしましょう。
さらに、マネジメントや人材育成などに携わった経験がある場合は、その旨も記載すると事業の実現可能性をより効果的にアピールすることができます。
専門学校や大学を卒業した年月日や勤務先、勤務年数などの基本的な情報と併せて、これまで従事した具体的な業務の内容や役職などを記載します。
コンテストで受賞した実績や社内で優秀な成績を収めた経験などがあれば、そのような情報も併せて記載することで、自分のスキルをより具体的に伝えることができます。
また、生花店は特定の資格等が無くとも創業することができますが、例えば「フラワー装飾技能士」などの資格がある場合は、その旨もアピールすることで審査で好印象を与えられる可能性が高くなるため記載しておくようにしましょう。
創業する生花店で取り扱う商品・サービスやその価格、セールスポイント、プロモーション戦略などを記載します。
また、ビジネスモデルを説明するために事業のフローや収益の仕組み、想定している顧客層、ならびに競合との差別化ポイントなども併せて記載することが大切です。
「取引先・取引関係等」の欄には、販売する生花の仕入れ先などの取引先を記載します。
仕入れ先が知り合いの事業者であったり、かつて勤めていた職場で担当した取引先などの場合は、その関係性も記載することで信頼度を高められる可能性が上がります。
「なかなか仕入れ先の目処が立たない」という方もいるかもしれませんが、仕入れ先が確定していない段階で創業融資に申し込むと、生花店創業に際しての準備が不十分であると見なされる恐れがあります。
そのため、創業融資を申し込むまでに複数の業者から見積もりを取り、事前に仕入れ先を決めておくようにしましょう。
また、一般消費者がターゲットの生花店の場合は、この項目に想定する顧客層や集客方法なども記載しましょう。
「必要な資金と調達方法」の項目は、創業計画書においてとりわけ重要な項目です。
創業するために必要な資金(設備資金・運転資金)と、その資金をどのような方法で調達するかを具体的に記載していきましょう。
設備資金については、単価が10万円以上のものは見積書を必ず用意し、見積先の名称と金額の内訳を記入していきます。
生花店創業時の設備資金の具体的な例としては、物件取得費用や内装・外装工事費用、冷蔵庫やショーケース、フラワーキーパーなどの設備・備品代などが挙げられます。
また、運転資金も客観性に乏しい記載はせず、業界の相場や事業計画をベースにした妥当な金額を記載することが大切です。
生花店の運転資金としては、生花などの仕入れ費用や広告費、お店の家賃や光熱費などが該当します。
加えて、創業融資の審査においては自己資金割合が非常に重要な項目となり、創業計画書内でも自己資金を記載する欄(「調達の方法」の箇所)があります。
そのため、自己資金は可能な限り多めに準備しておくことをおすすめします。
事業の見通しは、月平均の「売上高」「売上原価」「必要経費」「利益」を記載する項目となり、「創業当初」と「創業から1年後、もしくは事業が安定した段階」の数字をそれぞれ記載します。
ここで留意すべきポイントは、それぞれの数字を算出した根拠をしっかりと示すこと、そしてその計算式も併せて記載しておくことです。
これと言った裏付けもなく無計画な売上高を設定したり、経費額が市場相場からかけ離れていたりすると、事業計画全体の信憑性が低下し、審査などにマイナスな影響が出る可能性もありますので、ご注意ください。
生花店の創業・経営にあたり、法的に取得が定められている資格などはありません。
しかし、取得していることで生花店の経営にプラスに働く資格も存在します。
生花店の創業者や経営者が取得することが多い資格の例としては、以下のようなものが挙げられます。
■フラワー装飾技能士
■フローリスト検定
■フラワーデザイナー資格検定
■色彩検定
生花店の経営においてこういった資格は必須ではありませんが、専門的な知識があることでより良い商品・サービスの提供や顧客満足度の向上、それに伴う売上増加につながる可能性もあるため、生花店の創業に際して資格の取得を検討するのも有効な選択と言えます。
日本政策金融公庫の創業融資に申し込むためには、次の条件が求められます。
■創業前または創業後おおむね7年以内であること
■創業計画書(事業計画書)を作成し、またその内容を面談時に説明できること
■クレジットカード、ローンの支払い履歴が良好であること
また、自己資金をどの程度用意できているかといった点や、創業計画書の内容なども創業融資の審査に大きく影響するポイントになります。
「新規開業・スタートアップ支援資金」の融資額の条件は、設備資金が最大2,400万円、運転資金は最大4,800万円までと定められています。
また、返済期間の条件は以下のように規定されています。
●設備資金:最長20年(据置期間最長5年以内)
●運転資金:最長10年(据置期間最長5年以内)
ただし、融資額や利率、返済期間などは創業する事業の内容や、申請者の状況などに応じて異なりますので、詳細な情報に関しては日本政策金融公庫や専門家へ前もって確認しておくと良いでしょう。
日本政策金融公庫の創業融資審査を通過するためには、入念な事前準備が鍵となります。
■創業計画書(事業計画書)の作成
創業計画書では、まず創業する目的を明確にし、具体的な事業方針を示します。
次に、創業する事業のセールスポイントをわかりやすく伝えるために市場調査などを踏まえた競合に対しての自社の独自性や、対象となる顧客層を記していきます。
さらに、財務計画に関しても収益予測を具体的に示したものを策定することで、事業経営に継続性や計画性があることを強調します。
このように創業計画書を土台として、創業する事業の実現性と持続力をアピールしていくことが重要です。
※創業計画書の詳細は、こちらの記事もご覧ください。
<創業計画書とは?日本政策金融公庫の創業計画書のポイントを解説>
■自己資金の準備
創業にかかる資金総額に対しての自己資金の比率や、その自己資金をどういった手段で貯めたのかといった履歴も、創業融資の審査で鍵となるポイントです。
コンスタントに自己資金の準備をしてきたことは、資金管理や創業準備に計画性があることを裏付ける要素の一つとなり、審査でプラスに評価してもらえる可能性が高まります。
※自己資金について詳細は、こちらの記事もご覧ください。
<自己資金なしで創業融資を受けることはできるのか解説>
■信用情報を良好な状態に保つ
クレジットカードや各種ローンの支払いを複数回滞納していると、創業融資審査ではかなりのマイナスとなります。
そのため、支払いの遅れが発生しないよう創業前から心がけ、信用情報が良好な状態を保つよう気を付けることが大切です。
※信用情報の影響に関しての詳細は、こちらの記事もご覧ください。
<信用情報とは?創業融資における影響を解説>
創業融資の手続きの流れは以下のとおりです。
1.必要書類の準備(創業計画書、資金計画書、自己資金の証明資料など)
2.申し込み
3.日本政策金融公庫の担当者と面談の後、審査
4.融資決定・契約手続き
5.融資実行
創業融資の申し込みから実際に融資金が振り込まれるまでは、1か月前後の期間を要することが一般的であるため、資金繰りに困らないよう創業予定日から逆算して計画的に準備を進めていきましょう。
※日本政策金融公庫の創業融資の流れは、こちらの記事もご覧ください。
<日本政策金融公庫の創業融資の流れを解説>
本記事では、生花店創業を目指す方向けに、日本政策金融公庫の創業融資について解説しました。
生花店をはじめこれから事業を立ち上げたい方にとって、創業融資は非常に有効な資金調達手段ですが、審査に通るためには創業計画書の作成や十分な自己資金の確保など、入念な事前準備が欠かせません。
創業・開業時の資金が心許ないと感じる場合は、日本政策金融公庫が実施している無料相談を活用したり、創業融資支援を行っている専門家に依頼することで、資金調達の成功に繋がる可能性が高まります。
創業融資てづくり専門支援センターでは、累計4,500件以上の創業融資サポートおよび創業計画書・事業計画書の作成実績を有しています。
圧倒的な経験値やノウハウを活かして、着手金なしの完全成功報酬(一律固定)にてサポートさせていただくことが可能ですので、資金調達や開業資金でお悩みの方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。

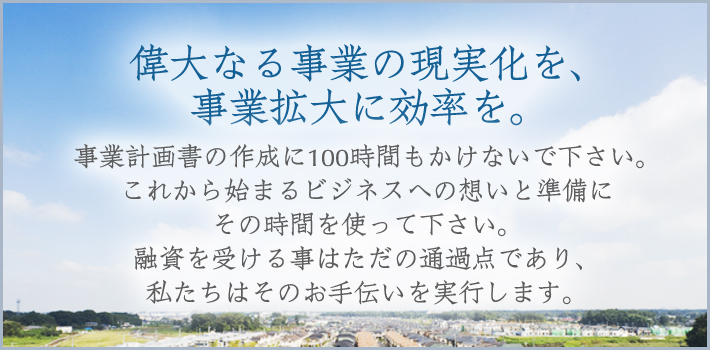
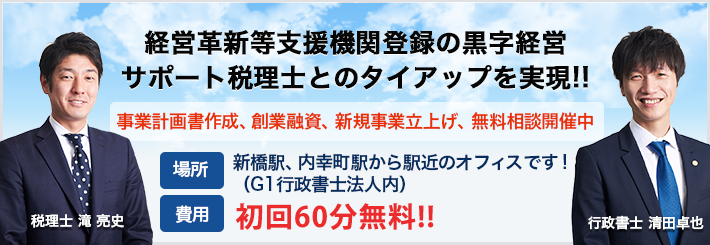
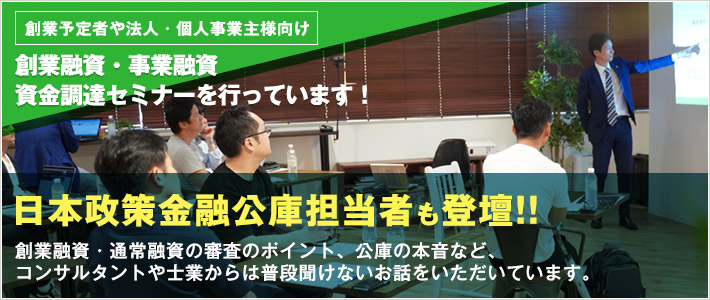



東京本社
〒100-0005
東京都千代田区丸の内1丁目1番1号
パレスビル5階
大阪支社
〒541-0046
大阪府大阪市中央区平野町3-2-8
淀屋橋MIビル3階
TEL / 0120-3981-52
FAX / 03-4333-7567
営業時間 月~土 9:00~20:00
メール問い合わせ 24時間対応

創業融資てづくり専門支援センター長の行政書士清田卓也でございます。
当センターは親切、丁寧、誠実さをモットーに運営しております。
事業計画書の作り方から創業融資まで、起業家・経営者様のほんのちょっとした疑問にもご対応させていただいております。
お気軽にご連絡下さい。