<最終更新日>
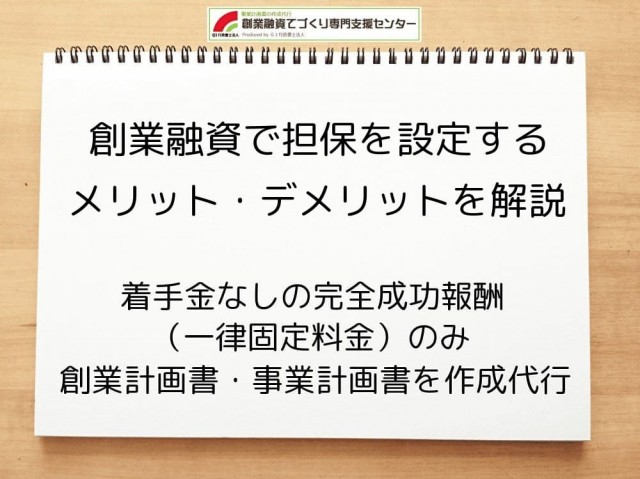 金融機関から融資してもらう場合、担保を設定するよう求められることも少なくありませんが、創業融資における担保とは一体どのようなものを指すのでしょうか。
金融機関から融資してもらう場合、担保を設定するよう求められることも少なくありませんが、創業融資における担保とは一体どのようなものを指すのでしょうか。
この記事では、どのようなものが担保となるのか、日本政策金融公庫の創業融資を申し込む際に担保を設定するとどのようなメリットやデメリットがあるのかなど、詳細やポイントを解説していきます。
担保とは、債務者が債務の保証となるような物を用意し、何らかの事情で返済ができなくなった場合は、債権者が担保を処分することで債権を回収できるようにする仕組みのことです。
担保は土地・建物・株式などの財産を担保にする「物的担保」と、債務者の返済が難しくなった時に保証人や連帯保証人などの第三者が返済義務を負う「人的担保」の2種類に分けられます。
一般的に、融資を受ける際に担保を設定することにはいくつかのメリットがあります。
ここでは、日本政策金融公庫で創業融資を利用する際に、担保を設定することでどのようなメリットがあるのかを解説していきます。
担保を設定することの大きなメリットの一つは、金利の優遇措置を受けられることです。
日本政策金融公庫の創業融資では「基準利率」と「特別利率」が設定されており、担保を設定すれば特別利率が適用されて、通常より金利が低くなります。
例えば1,000万円の融資の場合、金利が1%下がるだけでも返済総額に数十万円の差が生まれるため、金利の優遇は返済負担に大きく関わってきます。
ただし、実際の金利は担保の評価額や創業する事業の内容、申込者の状況などによって変わってくるため、担保を設定すれば必ず金利が優遇されるとは限らない点に注意が必要です。
また、日本政策金融公庫の基準利率や特別利率は毎月見直しが行われるため、創業融資に申し込む際は最新の利率や条件を確認しておくことが大切です。
担保を設定することで、融資金額が高くなるケースもあります。
これは、担保の評価額に応じて融資可能金額が影響を受けるため、評価額が高いほど比例して融資金額も高くなる見込みがあることや、公庫から「返済を滞納されても、担保分の債権は回収できる」と判断されることが関係しています。
ただし、「担保を設定すれば無条件に高額の資金を借り入れられる」というわけではなく、「無担保で創業融資を利用する場合の限度額よりも、担保を提供したほうが多めに借りることができる」という点を認識しておく必要があります。
日本政策金融公庫の創業融資で担保を設定することにはメリットがある反面、当然ながら次のようなデメリットも存在します。
担保を設定する大きなデメリットは、「資産を手放すリスクと隣り合わせになる」という点です。
土地や建物などの不動産を担保として設定した場合、抵当権が設定されることがほとんどであることから、融資の返済が難しくなった際は担保として設定した資産が競売などの形で売却されます。
そのため、担保に設定した資産は返済が終わるまで手放すリスクを常に抱えることになります。
さらに、担保に設定した資産を売り払っても、残りの債務を全額返済できないケースが大半です。
売却した額が融資の残額を下回っていれば、資産を失った後もなお残りの債務を返済していかなければならない可能性もあるという点にも留意しましょう。
担保を設定した場合、担保の不動産などが調査・評価され、登記手続きをする必要も出てきます。
そのため、無担保の創業融資の場合は申し込みから融資実行まで1か月前後に対し、担保を設定した場合はプラスで1〜2か月ほど余分に時間がかかることが多いという点がデメリットです。
よって、なるべく早く資金を調達したいという方は、創業融資で担保を設定するのは不向きと言えます。
創業スケジュールに余裕がない場合は、無担保の創業融資を活用することを選択肢として検討しましょう。
担保を設定する場合は、抵当権を設定するための登記手続きをしなければならないため、これに伴い様々な費用が必要となる可能性があります。
主な内訳は、融資金額に対し約0.4%かかる登録免許税や、印鑑証明書・登記事項証明書など登記にあたって必要な書類の取得費用、そして司法書士や弁護士に依頼する場合の報酬などです。
抵当権設定登記の申請は専門家に頼らず自分で行うこともできますが、専門的な知識やノウハウが必要になる部分が多く時間もかかることから、司法書士や弁護士に委任するケースが一般的です。
そのため、創業融資に担保を設定する場合は、無担保と比較して費用が余分にかかることになりますので、担保を設定するかどうかについては慎重に検討する必要があります。
創業融資をはじめとした日本政策金融公庫の融資で担保として設定できる対象は、土地や建物といった不動産などの「実物資産(物理的な形のある資産)」となります。
実物資産と同じ物的担保であっても、株式や投資信託などの金融資産(現金やそれに準ずる資産)は、日本政策金融公庫では担保として認められない可能性が高くなっています。
ただし、最終的に担保として認められるかは担当者の判断になります。
実物資産であっても必ず担保として認められるわけではなく、逆に金融資産でも条件次第で認められる場合もあります。
そのため、創業融資で担保の設定を検討している方は、事前に担当者に確認しましょう。
創業融資を申し込む際に担保を設定することには様々なメリット、デメリットがありますが、創業時の資金調達手段として多くの方が利用しているのは、原則無担保・無保証で利用できる日本政策金融公庫の創業融資制度です。
日本政策金融公庫の創業融資であれば、申し込みをする際に担保を用意する必要が無いため、万が一返済が難しくなっても自分の資産が差し押さえられる心配がありません。
また、創業期(事業開始前または事業開始後税務申告を2期終えていない方)であれば担保が無くとも金利の優遇措置を受けられるという点も魅力です。
更に担保を設定する必要が無いことから、創業融資に申し込んでから融資金が着金するまでの期間は1か月前後で済むことが多いため、創業準備をスピーディーに進めたい方にもおすすめの制度であると言えます。
本記事では、担保とはどういったものなのか、創業融資を申し込む際に担保を設定するとどのようなメリットやデメリットがあるのか、その詳細について解説しました。
日本政策金融公庫の創業融資制度は、原則無担保・無保証でありながら条件次第で金利の優遇措置を受けられ、担保が必要な場合と比較して融資実行までが早いため、様々な創業者から選ばれています。
創業時の資金調達方法について悩まれている方は、選択肢の一つとして検討してください。
創業融資てづくり専門支援センターでは、創業計画書・事業計画書作成やその後の申し込みにおいて4,500件以上のサポートを行ってきた経験と知識を活かして、着手金不要・完全成功報酬制(一律固定料金)でご利用いただける体制を構築しています。
「創業融資を活用して、事業の立ち上げに挑戦してみたい!という方は、ぜひお気軽にご連絡ください。

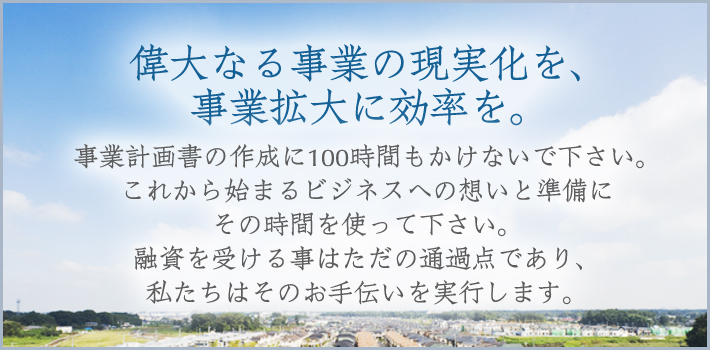
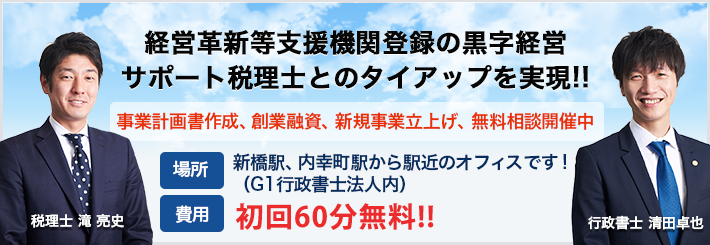
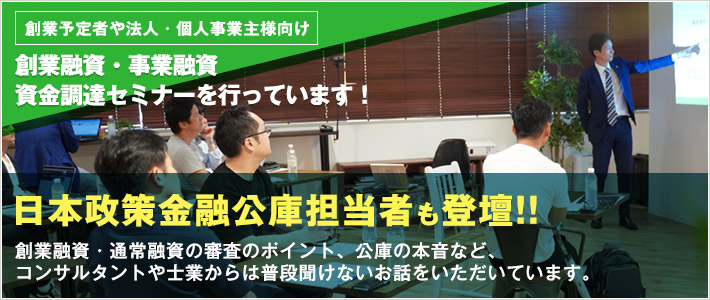



東京本社
〒100-0005
東京都千代田区丸の内1丁目1番1号
パレスビル5階
大阪支社
〒541-0046
大阪府大阪市中央区平野町3-2-8
淀屋橋MIビル3階
TEL / 0120-3981-52
FAX / 03-4333-7567
営業時間 月~土 9:00~20:00
メール問い合わせ 24時間対応

創業融資てづくり専門支援センター長の行政書士清田卓也でございます。
当センターは親切、丁寧、誠実さをモットーに運営しております。
事業計画書の作り方から創業融資まで、起業家・経営者様のほんのちょっとした疑問にもご対応させていただいております。
お気軽にご連絡下さい。