<最終更新日>
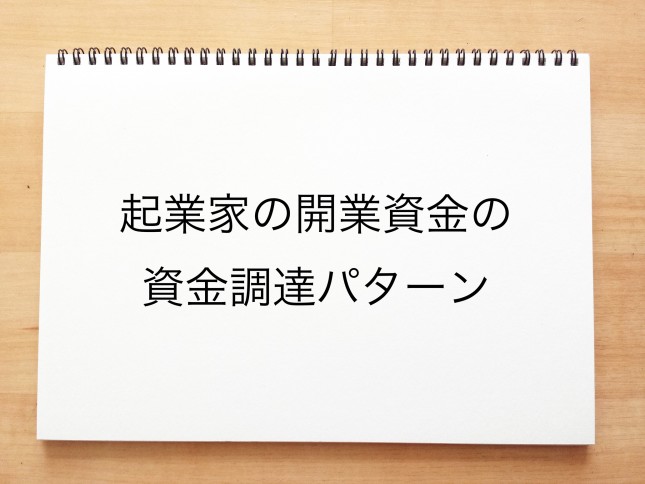
開業する際には、まとまった準備資金が必要になります。
初期投資やランニングコストが大きい事業を始めたい方や、現在の自己資金で賄えるのか不安という方は、資金調達が必要になってきます。
しかし、資金調達には様々な選択肢があるため、「どんな方法があるの?」「どれを選べばいいの?」と悩む方も多いのが現状です。
そこで今回は、開業時の資金調達手段や資金調達パターン、注意点などを詳しく解説します。
開業して事業をスタートさせるには、事業を継続していくための開業資金が必ず必要となります。
この開業資金は、事業の土台を築き、安定した運営を行う上でとても重要となるものです。
しっかりとした準備なくして、事業の成功は難しいと言えるでしょう。
開業資金として調達すべき金額は、事業内容や規模によって異なってきます。
例えば、飲食店や美容室のように店舗を構え、内装などに工夫が求められる事業は、多くの開業資金が必要になる傾向があります。
一方で、SOHO(自宅や小規模オフィス)系やインターネットを活用する事業などは、開業資金をそこまで必要とせず、比較的少額で始められる場合もあります。
ご自身の事業がどのタイプになるのかを具体的にイメージし、必要となる開業資金の概算を立てていきましょう。
また、安定的に黒字を出せるようになるまでの期間も開業資金の金額に影響します。
例えば、コンサルティングなどのスキルを提供して対価をすぐに受け取れる事業と、自社で新しいアプリケーションを開発・提供するなどの立ち上がりに時間がかかる事業とでは、運転資金(実際に事業を開始してから必要となる数ヶ月分の経費)として準備すべき金額が変わってきます。
開業後の売上見込みと経費をしっかりと計算し、余裕を持った開業資金の計画を立てることが大切です。
最低でも半年分、できれば1年分の運転資金を確保しておくことをおすすめします。
開業にあたって必要となる資金は、大きく分けて「設備資金」と「運転資金」です。
事業開始に必要となる店舗・事務所の取得費用、設備や備品の購入費用は「設備資金」、実際に事業を開始してから必要となる数か月分の経費は「運転資金」となります。
<設備資金>
店舗・事務所の取得費用、内装・外装工事費、事業に必要な設備・什器の購入費、許認可・登記関連費など
<運転資金>
人件費、オフィスや店舗の家賃、通信費、光熱費、消耗品費、月々の広告宣伝費、旅費交通費、外注費・委託費、サーバー代、サービス利用料など
こうした費用の全体像を整理し、開業資金の資金計画を明確にしておくことで、安心して事業をスタートすることができます。
開業資金の資金調達を考える前に、まずは貯金などの自己資金でどれだけ賄えるかを検討してみてください。
自己資金は返済の必要がない最も安定した資金源のため、できる限り準備をしておきたいものです。
また、自己資金はただ単に「お金がある」ということ以上に重要な役割を持っています。
■金融機関からの信頼につながる
自己資金は、事業を始めるにあたりどれだけ準備してきたか、その「本気度」を金融機関に示す大切な要素になります。
自己資金が全くない状態だと、「本当にこの事業を始めるつもりはあるのか?」と思われてしまう可能性も大いにあります。
また、融資審査においては、融資希望金額に対して自己資金の割合が多いほど金融機関からの評価が高まり、融資を受けやすくなる傾向があります。
「自己資金は〇割以上必要」という明確な基準はありませんが、一般的に資金総額の3割程度自己資金があると、融資の審査を通過する可能性が高まるといわれています。
■返済負担がない安心感が支えになる
自己資金は借入金ではないため、返済の義務がありません。
事業を始めたばかりで売上が不安定な時期には、これが大きな精神的支えとなり、事業の成長のための取り組みに集中しやすいというメリットがあります。
無駄な出費を減らしたり、計画的に貯蓄をしたりして、少しでも多くの自己資金を準備しておくと安心です。
提携する企業や取引先からの出資、または借り入れという形で資金を調達できる場合もあります。
企業側は事業の将来性や成長性に投資をします。
資金提供だけでなく、事業連携、販路拡大、技術的なサポートなど、資金以外のメリットにも期待できることが多いです。
ただし、出資を受けるということは、その企業が株主になるということになるため、経営の意思決定が創業者の意向だけでなく、出資企業の意向にも左右される可能性を考慮しておく必要があります。
企業側が特定のプロジェクトや取引を前提に融資をしてくれます。
通常の金融機関よりも事業内容への理解度が深く、柔軟な条件で借り入れることができる可能性があります。
いずれにしても、事業の将来性やメリットを相手企業に伝わるかがカギとなるため、しっかりとした事業計画を作成し、示すことが重要です。
家族や知人からの出資や借り入れの場合は、比較的低い金利や柔軟な返済条件で資金調達できる可能性があります。
ただし注意点として、借り入れの場合は人間関係に影響を及ぼすこともあるため、契約書を作成するなど、後々トラブルにならないよう以下のような取り決めややり取りを行うことが重要です。
■契約書の作成
必ず書面で「誰が、誰に、いくら、いつまでに、どのような条件で(金利の有無、返済方法など)」返済するのかを明記した契約書を作成しておくのが賢明です。
これは、親しい間柄であっても同様です。
■返済計画の共有
いつまでに、どのように返済していくのか、具体的な計画を相手にしっかりと説明し、同意を得ることが大切です。
■定期的な報告
事業の進捗状況や資金の使い道について、定期的に報告する機会を設けることで、相手からの信頼を保つことができます。
政府系金融機関の日本政策金融公庫や地方自治体の制度融資など、国や地方自治体が関わる金融機関から受ける融資です。
開業時は政府系金融機関である日本政策金融公庫はとても頼りになる存在です。
特に創業融資は、実績のない起業家が利用しやすい条件の制度です。
無担保無保証で申し込むことができ、金利が比較的低く返済期間も長めに設定できる場合が多いので、資金調達の際は積極的に活用を検討することをおすすめします。
<創業融資の特徴>
■実績がなくても利用しやすい
過去の融資実績がない方でも、事業計画や自己資金の状況によって融資を受けやすいのがメリットです。
■低金利
民間の金融機関に比べて、比較的低い金利で借り入れができることが多いです。
■長期の返済期間
返済期間を長く設定できる場合が多いので、開業後の資金繰りにゆとりが生まれます。
■無担保・無保証人
原則、担保や保証人なしで借り入れができます。
■制度融資と比べて着金するまでの期間が短い
制度融資は、自治体・金融機関・信用保証協会の3者が連携する融資のため、申し込みから融資金が着金するまで2~3か月程かかりますが、日本政策金融公庫は1か月前後で着金します。
ただし、誰でも簡単に借りられるわけではなく、しっかりとした創業計画書や事業計画書の作成や担当者との面談を通じて、事業への情熱や事業計画の実現性の高さ、借り入れの返済能力などを審査されます。
ご自身の事業や提供サービスがどのように社会に貢献し、収益を生み出すのかを明確に説明できるよう準備をしておくことが大切です。
地方自治体・金融機関・信用保証協会が連携して提供する「制度融資」も開業の資金調達先として有力な選択肢です。
信用保証協会が保証に入るため、民間金融機関の融資よりも通りやすくなるというメリットがあります。
<制度融資の特徴>
■民間の金融機関より借りやすい
万が一、事業者が融資を返済できなくなった場合に、信用保証協会が金融機関に対してその債務を肩代わりする保証に入るため、金融機関のリスクが軽減され、実績の少ない創業期の事業者でも融資を受けやすくなります。
■低金利
自治体によっては利子補給制度などがあり、金利負担を抑えられる場合があります。
注意点としては、申し込みから融資金の着金まで時間がかかるという点です。
制度融資は信用保証協会と金融機関のそれぞれが審査を行うため、申し込みから着金まで2~3か月程度かかる場合があります。
銀行、信用金庫、信用組合などから受ける融資です。
実績のない創業期には少々ハードルが高くなる先ですが、事業計画や担保次第で融資を受けられる可能性もあります。
注意点としては、日本政策金融公庫の融資や自治体・金融機関・信用保証協会による制度融資よりも、金利が高くなる傾向にあります。
助成金や補助金は、国や地方自治体が特定の政策目的を達成するために、条件を満たした事業者へ資金を交付する制度です。
最大の特徴は「返済の必要がない」ことですが、使った経費に対して補助を受けられるものであり、開業資金として先に受け取れるものではないため、そのニュアンスの違いは理解しておく必要があります。
注意すべき点としては、助成金・補助金は、応募期間などが限定されているものがほとんどです。
年間を通して常に募集されているわけではないため、最新の情報を常にチェックしておく必要があります。
また、申請すれば受け取れるわけではない制度もあり、その場合は多くの応募の中から条件に合致し、かつ事業内容の優位性が認められたものだけが採択されることになります。
当センターでは、補助金の申請サポートも提供していますので、補助金についてもお気軽にご相談ください。
開業資金の主な資金調達パターンとして考えられるのは、以下5パターンです。
法人に対する出資金で全てを補う場合は、資金調達にそれほど時間をかけることなく、すぐに事業をスタートさせることができます。
また、出資金は返済義務がなく、資金繰りの心配が少ないため、事業の拡大や新しい技術の開発、顧客満足度の向上など、本来の事業活動に集中しやすくなります。
自己資金で全て補う場合は、借入がないため金利や返済のプレッシャーがなく、事業に集中しやすい環境を作ることができます。
SOHO(自宅や小規模オフィス)やオンライン事業など、初期費用や運転資金が比較的少額で済む事業に適していますが、事業が拡大する際に追加の資金が必要になった場合に備えて、ある程度の自己資金は確保しておくと安心です。
自己資金だけでは足りないが、公的機関や民間の金融機関からの融資はまだハードルが高いと感じる場合に検討されます。
前述の通り、親しい間柄だからこそ、書面での取り決めや返済計画の共有など、誠実な対応が求められます。
ある程度の自己資金を用意することで、事業への本気度や計画的な準備を示し、不足分を日本政策金融公庫の創業融資や自治体の制度融資、民間金融機関の融資等で補うパターンです。
前述の通り、公的機関の融資は、金利が比較的低く、返済期間も長めに設定できるため、開業後の資金繰りの不安を軽減してくれます。
複数の調達先を組み合わせ、比較的大きな規模の資金調達を目指すパターンです。
この場合、それぞれの調達先に対して丁寧な説明をし、事業計画の一貫性を示すことが重要となります。
上記内容で開業資金を準備し、助成金・補助金の補助も受けられれば、資金計画において負担が少なくなります。
しかし、前述のとおり、助成金・補助金はいつでも補助を受けられるわけではなく、また、申請すれば100%受け取れるというものでもありません。
そのため、基本的には、助成金や補助金に頼らなくても事業を継続できるように計画を立て、助成金や補助金の募集があった際に活用できるものがあれば活用するという形がおすすめです。
創業計画書や事業計画書は、自分のアイデアを具体化し、将来のビジョンを示すだけでなく、資金調達の際にもとても重要な役割を果たします。
融資や出資する側の金融機関・企業は、創業計画書や事業計画書を通じて、その事業がどれくらいの資金を必要とし、どのように返済していくのか、どれ程のリターンが得られるのかを判断します。
創業計画書や事業計画書に必要な資金の内訳や調達方法を明確に記載することで、金融機関や企業からの信頼性が高まるため、必ず記載するようにしましょう。
総じて、事業をスタートしていくには「タイミングが重要」となるパターンも多くあることから、しかるべきタイミングに事業をスタートできるように、コツコツと事業計画を練っていきましょう。
今回の記事では、開業時の資金調達手段や資金調達パターン、注意点などを解説しました。
開業時には様々な資金調達先や資金調達パターンを理解し、ご自身に合った無理のない資金調達を行うことが大切ですし、資金調達のためのしっかりとした事業計画も必要となります。
当サイトを運営する創業融資てづくり専門支援センターでは、4,500件以上の創業融資サポートや創業計画書・事業計画書の作成支援に携わってきた実績を持ち、その経験や知見を活かして、着手金なしの完全成功報酬(一律固定)にて創業融資をサポートしています。
「創業融資に申請したい」「創業計画書や事業計画書の作成をプロにサポートしてほしい」という方は、お気軽にお問い合わせください。
>>次のページ
『 起業家には必見の創業時に受けられる融資限度額の参考 』
① 日本政策金融公庫の融資
② 創業融資支援の成功報酬はないのでしょうか?
③ 1000万円程の創業融資を受ける事は可能でしょうか?
④ 開業計画書を考える4つの視点
⑤ 開業時は日本政策金融公庫と銀行どちらが融資を受けやすいのでしょうか?
① 起業する前に知っておきたい21の知識
② 新規事業を成功へと導く立ち上げ時に検討すべき8つの思考
③ 資金調達を計画する時に知っておきたい考え方
④ 事業計画作成において把握しておきたい必要ポイント
⑤ 業界別の創業融資や事業計画書作成のサポート
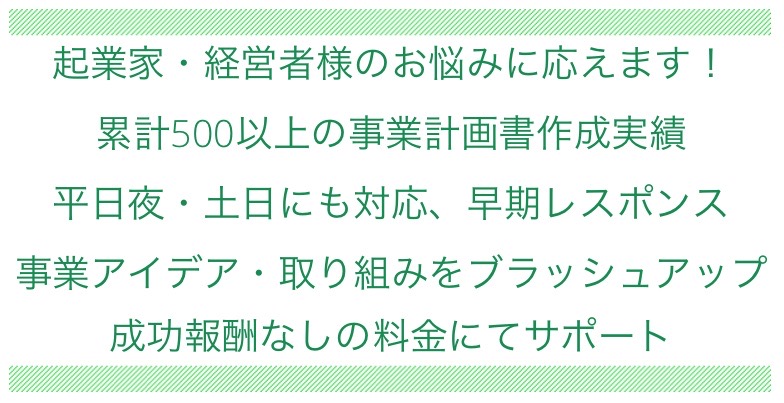

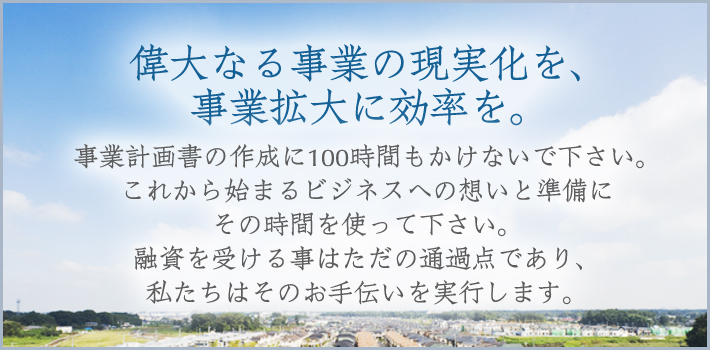
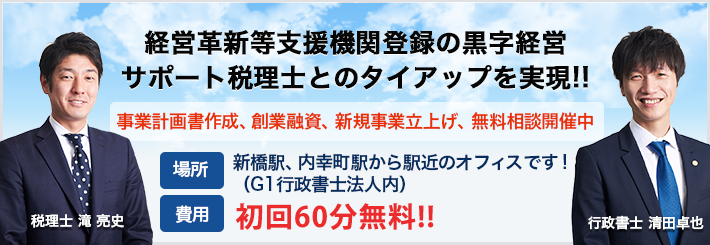
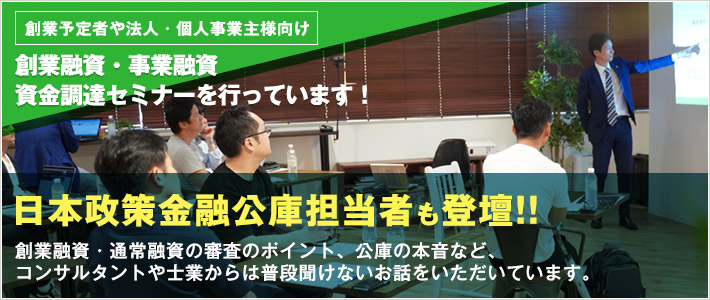



東京本社
〒100-0005
東京都千代田区丸の内1丁目1番1号
パレスビル5階
大阪支社
〒541-0046
大阪府大阪市中央区平野町3-2-8
淀屋橋MIビル3階
TEL / 0120-3981-52
FAX / 03-4333-7567
営業時間 月~土 9:00~20:00
メール問い合わせ 24時間対応

創業融資てづくり専門支援センター長の行政書士清田卓也でございます。
当センターは親切、丁寧、誠実さをモットーに運営しております。
事業計画書の作り方から創業融資まで、起業家・経営者様のほんのちょっとした疑問にもご対応させていただいております。
お気軽にご連絡下さい。